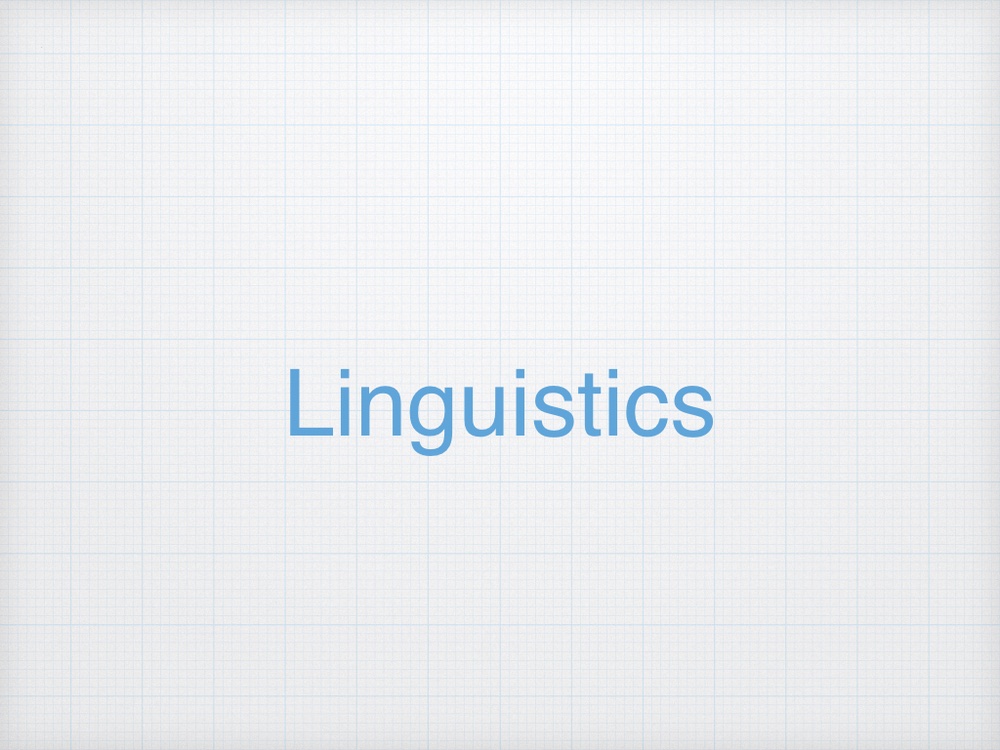ChatGPTのリサーチ機能
普段から愛用しているChatGPTだが,PlusユーザーでもDeep Research が使えるようになったので使ってみた.
以前のFelo AI Searchと比べてみてほしい.
今回は試しにVP内主語仮説についてまとめてみた.
VP内主語仮説(VP-Internal Subject Hypothesis)
VP内主語仮説(VP-Internal Subject Hypothesis, 以下VPISH)は、生成文法における統語理論上の仮説で、文の主語(外項)が文全体の主語位置ではなく動詞句(VP)内部の位置で基底生成されるとするものです  。この仮説によれば、主語は初期構造ではVPのSpecifier(Spec-VP)に位置し、その後統語上の必要に応じてTP(かつてのIP)のSpecifier(Spec-TP)に移動すると考えられます 。以下では、この仮説について1) 歴史的背景と提唱者、2) 理論的根拠、3) 統語構造への影響、4) 言語間の証拠、5) 反論や問題点――の観点から包括的に解説します。
1. 歴史的背景と提唱者
主語の位置に関する生成文法の見解は時代とともに変遷してきました。初期の標準理論(1950~60年代)では、句構造規則に基づき「文=S→NP VP」という規則が想定され、文主語はVPの外にあるNPとして構造化されていました 。例えば「John ate an apple(ジョンがリンゴを食べた)」という文は、当時はS(Sentence)の直下に主語NP (John)とVPが並ぶ構造として分析され、主語はもともとVPの外側に位置すると考えられていたのです 。その後、Xバー理論(1970年代、Jackendoff (1974, 1977) など)により全ての句範疇は最大投射としてSpecifierを持つという考え方が導入され 、IP仮説(Inflection Phrase; Chomsky 1981)では文全体をI(Infl)の投射とみなし、そのSpec-IPに主語が位置する構造が提唱されました  。つまり1980年代前半までは、「主語=Spec-IP(もしくはS直下のNP)」というのが一般的な枠組みだったわけです。
そうした中、1980年代後半に入ると主語の基底位置をVP内部に求める見解が現れました。Fukui & Speas (1986)、北川 (Kitagawa) (1986)、黒田 (Kuroda) (1988)、Koopman & Sportiche (1988/1991) などが相次いでVP内主語仮説 (VPISH) を提唱し、文法関係のより局所的・一般的な説明を目指しました 。Kitagawa (1986)は英語と日本語の主語位置を比較検討し、両言語で主語がVP内部に生成されることを示唆しました。またKoopman & Sportiche (1988)は英語・フランス語のデータから、全ての主語(能動文の主語でさえ)をVP内部で生成せざるを得ないと論じ、特に浮遊数量詞現象や準等位構造の振る舞いを根拠に挙げました  。Chomsky (1986)頃からのBarriers理論を経て、Chomsky (1995) の最小主義プログラムではVPISHが統語構造の基本前提として組み込まれ、動詞の外項を導入する独立の投射「小さいv (little v)」の存在が仮定されています 。つまり1990年代以降、主語はVP(正確にはvP)内部から派生し上位へ移動するという考え方が主流となり、VPISHは仮説というより標準理論の一部として定着していきました。
2. 理論的根拠
VP内主語仮説が提唱された背景には、従来の「主語は常にVP外」という分析では説明が難しかった理論的・経験的な問題が存在します。主な根拠として次の三点が挙げられます 。
• (a) 文法関係の局所性: 動詞による項の選択(下位範疇化)やθ役割(主語に対する意味役割)の付与は局所的な構造関係で行われます 。例えば動詞は隣接する要素(補部やSpecなど)にしかθ役を与えられないという原則があります。しかし主語がVPの外(Spec-IP)に最初から存在すると、動詞と主語が直接の統語関係になくなり、主語がどうやって動詞からθ役割(エージェントなど)を受け取るのか説明が困難です 。VPISHを採用し主語をVP内部(動詞の近接位置)で生成すれば、動詞が主語に直接θ役を与えることが可能になり、この局所性条件を満たすことができます 。
• (b) 意味的相関関係: 指示的主語を持つ文と非指示的な虚辞主語(expletive 主語)を持つ文のあいだに観察される意味表示の同一性もVPISHを支持します 。例えば英語の「John seems to be nice(ジョンが優しそうだ)」と「It seems that John is nice(ジョンが優しいようだ)」は表面的には主語が異なります(前者は John が主語、後者は it が形式主語)が、両者の意味解釈はほぼ同一です。このような場合、論理的には “John” が動詞 “seem” の主語(経験者)であると考えるのが自然であり、VP内部で “John” にθ役割を与えた上で、表層では “it” が主語位置を占めると考えれば、両構文の意味的類似性を統一的に説明できます 。同様に「There is a man in the garden(庭に男がいる)」のような存在構文では、表層主語 there は意味的内容を持たず、真の主語 “a man” がVP内に残っていると解釈できます。このような虚辞・存在構文の意味と統語のずれも、VPISHにより「主語はVP内に生成され、その位置で意味役割を受け、表層では独立の主語位置に別要素(虚辞)が現れる」という形で整合的に捉えられます。
• (c) 指定部の普遍性: Xバー理論においては全ての句範疇はSpecifierを持つとされています 。VPも句範疇である以上、本来はSpec位置を持つはずですが、従来の分析で主語をVP外に置くとVPのSpecが常に空位になってしまいます。この点に着目し、VPのSpecにこそ主語が存在すると考える方が理論的に自然だとする議論があります 。特に生成文法では対称性の原理などから構造の統一性を重視するため、VPだけが例外的にSpecを投射しないと仮定するより、他の句と同様にVPにもSpec(=主語位置)が存在し主語NPが投射されると考える方が望ましいのです。
以上のような理由から、VP内主語仮説はθ役割の付与規則の局所性を保ち(a)、虚辞を用いた構文と通常構文の意味対応関係を説明し(b)、**Xバー理論に基づく構造的一般性を確保する(c)**理論的メリットがあります 。とりわけ (a) の観点は重要で、VPISHの採用によって「主語も動詞と同じVP内で生成されるため、目的語などと同様に動詞から直接統語・意味的関係を受ける」という対称的な構図が得られます 。この点は、後述する浮遊数量詞のような経験的現象の説明にも寄与しています  。
さらに、最小主義プログラム (Minimalist Program) においてVP内主語仮説は洗練された形で組み込まれています。Chomsky (1995)以降の最小主義では、句構造はMerge操作により構築されるため、まず動詞と目的語からなるVPが形成され、次に動詞の外項(主語)を導入するための機能的投射として“小さいv (little v)”が追加されるというモデルが採用されます 。この v は語彙的なVとは別個の述語項構造を担う要素で、主語(外部項)にθ役割を付与するヘッドと位置づけられています 。主語はvP(=小さいvの句)のSpecにMergeされ、これがVP内部(より正確にはvP内部)に主語が生成されることを意味します。最小主義ではD-構造やS-構造といったレベル区分を設けませんが、このように構造構築の初期段階で主語をvP内に配置することで、GB時代の「主語はD-構造でVP内、S-構造でIP内に移動」という考えを引き継いでいるのです 。要するに、VPISHはミニマリスト理論の下では「vP内主語仮説」として再解釈され、依然として有効な概念となっています 。
3. 統語構造への影響
VP内主語仮説を採用すると、文の派生過程において主語の位置と移動に関する新たな構図が生まれます。主語がVP(vP)内部に基底生成された後、表層的には通常Spec-TP(IPのSpec)に現れるためには統語的な移動 (主語繰上げ) が必要です 。この移動とそれを要請する要因について整理します。
• 主語の派生位置とSpec-TPへの移動: VPISHによれば、主語NPはまずVP内部(典型的にはvPのSpec)に配置されます 。しかし最終的な文では、多くの言語で主語が文頭に現れるため、主語はVP内の基底位置からTPのSpecまで移動する必要があります 。生成文法では、主語がこのように構造内をA移動して文頭に来る現象を主語の上昇 (Subject raising) と呼びます。例えば英語の平叙文「John ate an apple」であれば、主語 “John” は初期状態では [VP __ eat an apple ] の位置にあり、その後 [TP John [T ate] [VP __ eat an apple ] ] という構造へと移動します 。この移動はD-構造からS-構造への派生とみなすこともできますし、最小主義的には構造構築途中でのMergeとAgreeによる再配置とみなしてもよいでしょう。
主語がVP内で基底生成されSpec-TPへ移動する構造の例を示します 。上図は「John ate an apple(ジョンがリンゴを食べた)」の統語構造をVP内主語仮説に基づいて表したものです。もともと主語”John”はVPのSpecに位置し、動詞”eat”から直接θ役(エージェント)を受け取ります。その後、時制要素I(PAST)の投射であるTPのSpecへ移動し、文全体の主語の位置を占めます(図中の矢印) 。この移動により表層的な語順「John - ate - an apple」が得られますが、基底位置には主語の痕跡 (trace) が残り、そこにおいて動詞とθ・統語関係を結んでいると解釈されます。
• Extended Projection Principle (EPP) と移動要請: 主語をSpec-TPへ移動させる主要因の一つが拡大射映原則 (EPP) です。EPPは**「全ての文は主語(構造的主語位置)を持たねばならない」という原則で、Chomsky (1981)で提唱されました 。EPPにより、たとえ主語が語義的に空 (expletive) であっても文法上はSpec-TPに何らかの要素を配置する必要があります。VPISHの下では、VP内にある主語をSpec-TPに上げることがEPP要件を満たす自然な方法となります 。例えば英語では、主語が明示されない無主語文は許されず、必ず形式主語 (it, there) などでSpec-TPを埋めます。VP内主語仮説を取ると、こうした形式主語構文も「本来の主語はVP内に留まり、EPPを満たすためだけに形式主語が挿入されている(もしくは本来の主語は移動せず形式主語で穴埋めしている)」と分析できます。このようにEPPはVP内から主語を引き上げる誘因**となっており、VPISHと補完的な関係にあります 。
• 格理論と一致による要請: 主語を移動させる他の要因として、格付与 (Case assignment) と一致 (Agreement) の要請があります 。GB理論では、主語の名詞句には主格 (nominative Case) を与える必要がありますが、主格は通常有限のI (Infl/T)によって付与されると考えられていました。主語がVP内部にとどまっていてはIから十分な統語関係(支配やSpec-Head関係)を得られず、格フィルターに違反する恐れがあります。そのため主語はSpec-TPに移動し、IやTと直接関係を結ぶ位置で主格を獲得する必要があるのです 。同様に、動詞の人称・数一致も主語が近接していなければ成立しにくいと考えられます(※最小主義ではAgreeにより長距離一致も可能とされますが、少なくともGB期には主語-述語の一致は構造的隣接関係で説明されました)。主語をSpec-TPに移動させれば、統語構造上Tと主語が直接対応し、主格の付与と述語との一致が円滑に行えるわけです 。総じて、VPISHの枠組みでは**「主語は意味役割取得のためVP内に、生来的な格・一致要件のためTPへ」**という二段階配置が導入されることになります。
• 派生構造とEPPの相互作用: 主語がVP内部から移動してくる場合、派生の経路にある各Spec位置を経由すると考えられます。例えば複合時制(助動詞を含む文)のようにTPが二つ以上重なる場合、主語は下位のvP/VPから逐次すべての中間のSpec位置を経由して最終的な主語位置に達するとされます 。これは、主語移動が経由しない位置に浮遊数量詞を置くことができない(後述)事実などから裏付けられています 。またChomsky (1995)以降、一部の研究者はEPPをTの持つ形式素性(例えば「D素性」や「EPP素性」)として捉え、主語のMoveを引き起こすトリガーとみなしました。これにより、言語ごとの違い(例えばNull-subject言語ではTのEPP素性が弱く主語が移動しない等)も説明しやすくなっています 。実際、日本語などの主語省略言語では、主語が明示的に現れない場合でも文が成立するため、EPPの充足方法に言語差があると考えられます(日本語の場合、暗示的な主語プロ(PROP)がSpec-TPを満たすか、あるいはEPP自体が常に必要とはされないという提案があります)。以上のように、VPISHは格・一致・EPPといった統語原理と組み合わさって主語移動を説明する総合的な枠組みを提供します。
4. 言語間の証拠
VP内主語仮説は様々な言語の現象によって支持されています。英語をはじめ、多くの言語で主語がVP内に生成されると仮定することで説明が容易になる事象が観察されています  。ここではいくつかの代表的な証拠を言語別に紹介します。
• 英語: 英語では以下のような現象がVPISHを裏付けます。
• 存在構文 (Existential there-construction): 「There is/are + 名詞句 + …」の構文では、表面上 “there” が主語の位置にあり、実質的な主語(存在する対象)は動詞の後ろに置かれます。例えば There is a man in the garden. では a man が意味上の主語ですが、文頭は there です。この場合、“a man” はVP内に留まっていると考えると自然です。実際、動詞 is の人称・数は a man に一致して単数形になっており、Tは離れたVP内の”a man”と一致関係を結んでいることがわかります。VPISHによれば、a man はVP内の基底位置にあり、EPPを満たすために there が挿入された(主語位置を占めた)構造だと分析できます。これは主語が必ずしも最初からSpec-TPにいなくても文法が成り立つことを示す例であり、主語の基底位置はVP内である可能性を示唆します。
• 浮遊数量詞 (Floating Quantifier): 主語と共に意味をなす数量詞が主語から離れて現れる現象も重要な証拠です。例えば (All) the students have (all) left. のように、数量詞 all を主語 the students の後ろや助動詞の後ろに置くことができます 。(All) the students… に対して the students … all … の語順が可能であることは、数量詞 all が元々は名詞句内にあったものが主語の移動によって取り残された結果と考えられます 。実際、The students have all left. という文では all が主語に対応する浮遊数量詞で、主語 the students がもとの位置を離れTPに移動した痕跡付近に all が残留していると分析できます。この分析によれば、本来の構造は [VP all the students [V left]] であり、the students だけが上方へ移動して [TP the students [VP all __ left]] となったと説明できます  。このように考えることで、数量詞と名詞句の修飾関係を特別な規則なしに統一的に扱えるという利点があります 。実際、別々の統語位置にある数量詞と名詞句を関連付けるために特殊な規則を設けるより、VPISHの枠組みで残留移動として説明する方が簡潔です 。英語の浮遊数量詞は主語に限らず目的語の場合もありますが、少なくとも主語について言えば、この現象は主語が一度VP内に存在したことの痕跡と捉えられるのです 。
• 動詞句省略 (VP Ellipsis) や倒置: 英語では助動詞の後ろのVP部分を省略できる現象があります(例: John will win the race, and Mary will [win the race] too.)。このとき省略されるのはVP内部の内容であり、主語は省略の対象になりません。これは、主語がVPとは別の構成要素であることを示唆します。伝統的分析でもVPは主語を含まないため同様に説明できますが、VPISHのもとでは「主語は省略前にすでにVPから抜け出していた」と考えることができます。つまり、省略の時点でVP内には主語が残っておらず、従って主語以外の部分だけが消去されるというわけです。この分析は、VP前置 (VP fronting) の場合にも言えます。例えば ”[Win the race], John certainly will __.” のようにVPを文頭に移動する場合、主語”John”は一緒に移動しません。これも、主語がVPの一部ではなく別位置にある(あるいは移動済みである)ことを示すものです。
• その他の証拠: 英語では他にも、「付加疑問 (Tag Question)」で主語代名詞と助動詞が参照する内容、否定極性項目の主語への作用域効果、副詞配置による主語の解釈(例えば Only John will all solve the problem のような構造)など、主語が底層ではVP内にいると仮定することで説明が容易になる事例があります。中でもalsoの例が興味深いです。 に示されているように、John also teaches semantics to Tom. という文の also は通常直後の要素を修飾しますが、「ジョンもまた教える」という解釈(主語に係るalso)が可能です。これは also の右側にある John を修飾しているとみなさねばならず、一見規則違反です。しかし John がVP内にいた段階で also John(ジョンも)という関係が成立していたと考えれば、この意味を容易に導けます 。以上のように、英語ではVPISHを支持する微妙な現象が数多く指摘されています。
• 日本語: 日本語は主語が省略されやすく、また語順も比較的自由ですが、VPISHは日本語の統語にも影響を及ぼします。日本語の代表的な証拠は数量詞の遊離です。例えば 「学生が3人来た」(複数の学生が来た)という文では、本来 3人の学生 と一塊になるはずの数量詞 3人 が主語名詞句 学生 から離れて現れています。この現象は英語と同様、主語がVP内部で数量詞とともに生成され、その後主語だけが移動した結果と考えられます。実際、“学生が3人来た” は深層構造では ”[3人 学生が] 来た”(主語句の内部に数量詞がある)であり、学生 が上位に移動して 学生が [ __ 3人 ] 来た のような構造になったと分析できます。その証拠に、日本語でも数量詞の分布には制限があり、主語が通過する位置(典型的にはVP内部や場合によっては中間的なvPの位置)以外には現れません。例えば 「学生がリンゴを3個食べた」(学生がリンゴを3つ食べた)では、3個 は目的語 リンゴを に付随する数量詞ですが、リンゴを3個の順でしか現れず ?3個リンゴを食べた のような順序は不自然です(主題化等を除けば)。一方で主語の数量詞は 学生が3人来た/3人の学生が来たのように出現位置が変わりえます。この差は、主語数量詞は主語が動いた後にその元位置に残留できる(=VP内部に留まれる)のに対し、目的語数量詞は目的語がその場に留まるため残留の形にならない、と解釈できます。以上から、日本語においても主語はVP内で数量を含む名詞句として生成されうることが示唆されます。
また、日本語のある方言の研究では、主格「が」との互換的に現れる形式「の」を持つ主語(例:肥筑方言のノ格主語)がvP内に留まるという主張もあります 。これによれば、日本語でも主語の位置には2種類あり、表層で「が」を伴う主語はSpec-TPに移動するのに対し、「の」の主語はより下位(おそらくvP内部)に留まっているとされています。このような言語内変異の分析も、VPISH/vPISHの視点から説明が試みられています。
さらに、日本語は主語を明示しなくても文が成立する(null-subject, pro-drop)という特徴があります。この場合、統語構造上は主語位置に空の代名詞(pro)が存在すると考えられますが、そのproがどこに存在するかも議論になります。VPISHに従えば、pro主語も元はvP内部に生成され、その後Spec-TPに移動したとみなすか、あるいは最初からSpec-TPに直接挿入される(EPP充足のため)か、いくつかの分析がありえます。しかし一般的には、日本語の主語省略文でも概念上は「何者かが…する」という主語が想定され、そのθ役割はVP内部で付与されていると考えた方が妥当です。したがって、日本語においても主語(省略されていても)は基本的にVP内で述語と意味関係を結ぶというVPISHの主張は当てはまるといえます。
• 他の言語: VP内部の主語に関する証拠は他の多くの言語にも見られます。
• フランス語: フランス語でも英語同様、浮遊数量詞の事例があります。例えば Tous les enfants ont vu ce film.(子供たち全員がその映画を見た)と Les enfants ont tous vu ce film.(子供たちは全員その映画を見た)では、数量詞 tous(全員)が主語 les enfants(子供たち)と離れて動詞後方に現れる後者の語順が可能です 。Sportiche (1988)はこのようなフランス語の例を詳細に分析し、主語 les enfants がもともとVP内部にあり数量詞 tous を伴っていたが、les enfants だけが前に移動した結果 tous がVP内に残留したと説明しました  。この分析により、数量詞 tous が離れていても les enfants を修飾できる理由が明確になります。またフランス語では非人称構文(Il ~構文)もあり、Il est arrivé trois étudiants.(3人の学生が到着した)のように il(英語のthereに相当)が主語位置に置かれ、実際の論理主語 trois étudiants(3人の学生)が動詞の後に来る構文があります。これもVPISHで、trois étudiants はVP内(原文では過去分詞arrivéの主語項)に留まり、il が主語位置を埋めていると考えられます。フランス語は主語の明示が必須なので il を入れますが、実質的な主語は下位にあるという点で、英語の存在構文と類似しています。
• ドイツ語: ドイツ語は主要部後置(SOV)の言語ですが、並列構造や一部の無主語文でVPISH的な分析がされます。例えばドイツ語でも天候表現では非人称の es(それ)が主語に立ちます(Es regnet.「雨が降っている」)が、この es は特定の指示対象を持たない形式主語です。VPISH的には、日本語同様に意味役割上の主語(雨など)はVP内にあり、es が文法上挿入されているとみなせます。またドイツ語の等位接続で、片方が受動文・もう片方が能動文の場合の特殊な振る舞いもVPISHで説明可能です。Rossの等位構造制約(CSC)によれば、一方の等位項からのみ要素を抜き出すことは禁止ですが 、受動文と能動文の等位接続では表面的に主語位置が異なるため例外的に見えます 。しかし受動文の主語は元々VP内(他動詞の目的語位置)に生成されているとする見方をとり、能動文の主語と共に両VPから同時にATB抽出されたと分析すれば、この例外も制約違反ではなくなります  。このようにドイツ語でも、VP内主語仮説は微妙な統語事実の整合的な説明に役立っています。
• 中国語: 中国語は主語の省略が可能で、また主語を文末近くに置く倒置構文もあります。例えば 来了一个人。(来た-一人の人, 「一人の人が来た」) という中国語文は、動詞 来了(来た)の後に主語 一个人(一人の人)が現れており、英語に直訳すると Came a man. に相当します。このような構文では、中国語には英語のような there や it は使われず、主語が表面上VPより後ろに留まる形になっています。これは中国語では必ずしもEPP(主語位置を埋める原則)が強制されず、主語がVP内(動詞の後)に現れることを許容していることを示唆します。生成文法的にいえば、中国語ではT(時制)に主語を前に出す強い素性が無く、主語がvP内部にとどまったままでも文が成立する、と分析されることがあります。このような主語残留型の構文は、中国語のみならずイタリア語などのNull主語言語でも報告されており、言語によって主語の移動要件(EPP素性の有無)が異なる可能性が示されています。
• VSO型言語: アラビア語やケルト語(例えばアイルランド語)のようなVSO語順の言語もVPISHの有力なサポーターです。これらの言語では文が「動詞-主語-目的語」の順で現れるため、一見主語がVPより後ろに位置しているように見えます。標準的な分析では、動詞がIやCの位置まで移動して文頭に立ち、主語はVP内に留まっていると考えられます。その結果、表面的にV-S-Oの順序が得られます。この分析はVP内部に主語位置があることを前提にしており、もし主語が初めからTPのSpecにいたならばVSO語順を得るのは困難です。実際、アイルランド語の研究では、動詞がC位置へ倒置した際に主語が依然としてVPの後ろに残っている証拠(否定辞や副詞の位置関係など)が示されています。McCloskey (1997)はアイルランド語のデータを詳しく分析し、VSO語順は主語がvP内に留まり、動詞のみが上昇した結果であることを論証しています(さらに、その際にも主語はθ役をVP内で受けている点を強調しています) 。このように、VSO型言語は主語が常に文頭に現れるとは限らないことを明示するため、VPISHを支持する重要な類型といえます。
以上のように、多言語にわたる証拠がVP内主語仮説の妥当性を裏付けています。英語やフランス語の浮遊数量詞現象は特に広く知られる直接的証拠であり  、加えて存在構文や主語倒置、能動受動の混合等位構造といった様々な現象もVPISHによって整合的に説明できます  。日本語や中国語のように主語が表面に現れない場合でさえ、主語がVP内部で述語と関係を結んでいると考えることで、意味役割付与の一般性や他言語との共通性を維持できます。したがって、VP内主語仮説は言語類型論的にも普遍的な示唆力を持つといえるでしょう。
5. 反論や問題点
VP内主語仮説は現在では広く受け入れられているものの、提唱当初からいくつかの反論や懸念も提示されてきました。ここでは主な論点を挙げ、関連する代替説や理論の展望について述べます。
• EPPの扱いに関する批判: 一部の研究者は、VPISHがExtended Projection Principle (EPP) とセットで導入されることに批判的です。すなわち「主語をVP内に置く」という仮説を採用すると、結局は「Spec-TPが空にならないよう主語を移動させねばならない」というEPPを別途仮定する必要が生じます 。これは理論の簡潔性を損なう可能性があります。最初から主語をSpec-TPに基底生成しておけばEPPを導入せずに済むのではないか、という指摘です。要するに「VP内→TPへの主語移動」という二段構えを設定するより、「初めからTPに主語を置けば移動もEPPも不要ではないか?」という疑問です。この批判に対して支持派は、前述したθ役割付与の局所性や浮遊数量詞の説明力などVPISHの利点がそれに勝ると反論します。また最小主義では、EPPは恣意的な原則ではなくTの持つ素性要件にすぎないと捉え直されており、言語ごとにEPP素性の強弱を設定できるため、主語移動の有無も統合的に説明できるとされます。例えばNull-subject言語ではTのEPP素性が弱く、主語を必ずしも移動させない(主語がvP内に留まる/プロで代用される)といった具合です。このようにEPPの形式化を進めることで、VPISHとEPPの関係は調整可能であり、大きな不整合とはみなされなくなっています。ただし依然として「主語位置を常に投射するEPP」は説明的ではないとの指摘もあり、EPPを他の原理(例えば項の構造的必要性や語順の派生的結果)に還元する試みも続けられています。
• Spec-TP基底生成という代替: VPISHへのオルタナティブとして、主語を初めからSpec-TPに生成する説も再考されることがあります。これは伝統的な句構造規則による見方に戻る形ですが、前述の通りその場合は動詞と主語の結び付きを別の仕組みで説明しなければなりません。例えばθ役割を遠隔付与する特別な機構を設ける、あるいは数量詞遊離を解決するために主語から数量詞だけを移動させるルールを追加する、といった必要が生じます 。しかしこれらは理論を複雑化させる上に、結局VPISHが自然に説明する事実を二度手間で記述することになるため、現在の主流派にはあまり支持されていません。実際、GB理論ではD-構造/S-構造の区別を用いて主語の二重位置を公式化しましたし、最小主義以降は構造構築の経路としてVP内部→TPへの主語配置がデフォルトとなっています。もっとも、言語によっては主語が常に文頭に現れVP内主語の痕跡が見えにくい場合もあり、そのような場合には表層構造のみを重視して「主語は常にSpec-TPにいる」とみなす記述も可能ではあります。しかし深層的・統語的な一般化を優先する生成文法の立場からは、やはり全言語に共通の普遍文法としてVP内主語位置を想定するほうが説得力があると考えられています。
• VPとvPの区別: VPISHが提唱された当初は、主語が「VP」のSpecに生成されると表現されました。しかし1990年代以降の発展でVPは分割され、vP(小辞句)とVP(動詞の補部句)に分かれるという見解が一般化しました(Larson 1988のVPシェル分析やChomsky 1995のv導入)。このため最近では「vP内部主語仮説」とも呼ばれ、実質的には同じ内容を指します 。vPは動詞の外項を導入する位置であり(=主語のθ役割付与位置)、VPは動詞の内部項(目的語など)を含む位置です。主語はvPのSpecに、目的語はVの補部にそれぞれ生成されるという形に細分化されたわけです。この変更自体はVPISHの精神を引き継ぐものですが、いくつか議論もあります。例えば、日本語の主語位置に関して舘石 (Tateishi 1994) は主語がVPの外に生成されると主張しましたが、吉本 (Yoshimoto 1999) はそれを踏まえつつ「vPの存在を認めれば両者は両立する」と述べています 。つまり「日本語の主語はVPの外だがvPの中である」という折衷案で、VPISHをvPISHとして解釈し直した形です。このように、最新の理論ではVP内主語仮説はvP内主語仮説として位置づけられ、より精緻な構造で主語の基底位置を捉え直しているといえます。
• その他の問題点: 一部の批判者は、VPISHに関連して統語範疇の混在や派生の複雑さを指摘することがあります。例えばVPISHでは、文の派生中に一時的に「主語のないTP」や「外項のないvP」が存在する局面が生じます。これは理論的には問題ないのですが、不必要な派生段階だとみなす向きもあります。また、ある段階で主語が複数箇所(基底位置と派生先)に存在するように見える(片方は痕跡)ため、概念的に分かりにくいという指摘もあります。ただし生成文法では痕跡やコピー理論は標準的な考え方であり、これらは大きな欠点とはされません。むしろ、VPISHを採用しない場合には浮遊数量詞のような現象を説明するために余分な変形規則が必要となり、かえって複雑になることから、総合的に見てVPISHの方が経済的だと評価されています 。
総じて、VP内主語仮説に対する直接の反論は限定的であり、主要な生成文法の枠組みの中ではVPISHはほぼ標準理論として受容されています。現在の研究の焦点は、VPISHそのものの是非よりも、それを前提とした上で主語移動の諸条件(EPP素性の起源、一致・格とのインターフェース、各言語の違い)をどう最適に説明するかという点に移っています。例えば、最新の最小主義理論ではフェーズ理論によりvPが意味的完結単位(=位相)になると考えられ、主語がvP内部で与えられるθ役割がそのフェーズで確定し、主語は上位フェーズ(CPなど)へ移動するといった見通しが得られます。このようにVP内主語仮説は、主語の統語的位置に関する我々の理解を深め、文構造の普遍的特徴を捉える基盤として機能してきました。今後も各言語の詳細なデータとの照合や、主語位置と情報構造(焦点・トピック)との関係などさらなる研究が進められ、VPISHは統語理論の中で引き続き重要な位置を占めていくでしょう。
参考文献: Chomsky (1981, 1995), Kitagawa (1986), Sportiche (1988), Kuroda (1988), Koopman & Sportiche (1991) ほか   。