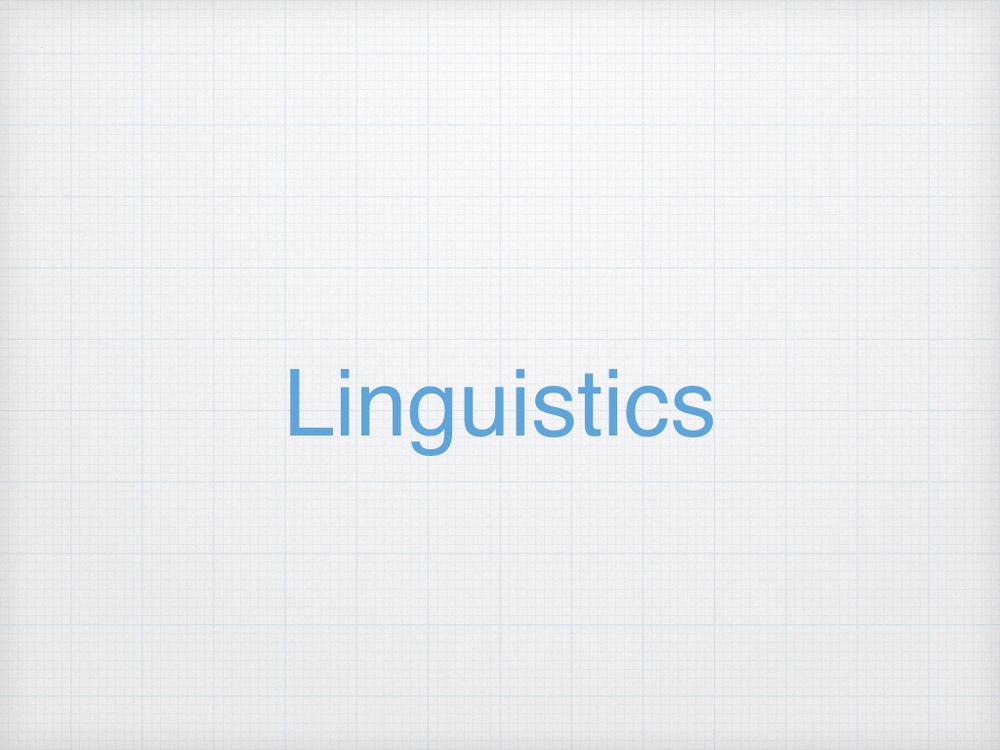語の形成における3つの立場について
人間が言語を使用する際、特に文を発話する場合には、意味の単位である語を文法規則に従って組み合わせることで、文を構成する.
言い換えれば、語という記憶された要素を基に、何らかの計算処理を通じて文が生成されていると考えられる.
しかし、Itoh (2019) はこのような単純なモデルに疑義を呈する.
語とは記憶された要素であると同時に、しばしば複数の形態素から構成されるため、語=記憶、文=計算という単純な等式は成立しないという.
たとえば、「形態論研究」という語は以下の三つの形態素に分割可能である.
- 形態
- 論
- 研究
このように複数の形態素がどのように処理されて一語を形成しているかは、文生成とは異なる独立の問題である.
したがって、語レベルにおける処理も理論的検討の対象となる.
語の形成がいかなる部門で処理されるかについては、形態論研究において以下の三つの立場が存在する (Itoh, 2019).
- 語彙主義 (lexicalism)
語の形成は語彙部門 (lexicon) で行われるとする立場.
複数の形態素を組み合わせた語は、単位として記憶される. - 統語部門主義 (syntactic approach)
語形成は語と同様に統語構造の生成過程で生じるとし、構文規則の延長であるとする立場. - 混合モデル (mixed approach)
語形成には語彙的処理と統語的処理の両方が関与するとする立場.
これらの立場の対立は、語形成が文法能力のどの部分に属するかという問いに直結しており、形態論と統語論の接点を考える上で重要な意味を持つ.
形態素の組み合わせとその処理が、文法体系全体の理解にどのように寄与するのかを探る点で、今後の理論的展開が期待される領域である.
参考文献
- 伊藤たかね. (2019). 「語」 のレベルの脳内処理から見えること── 言語学と脳科学の協働に向けて──. 認知神経科学, 21(3+ 4), 209-215.