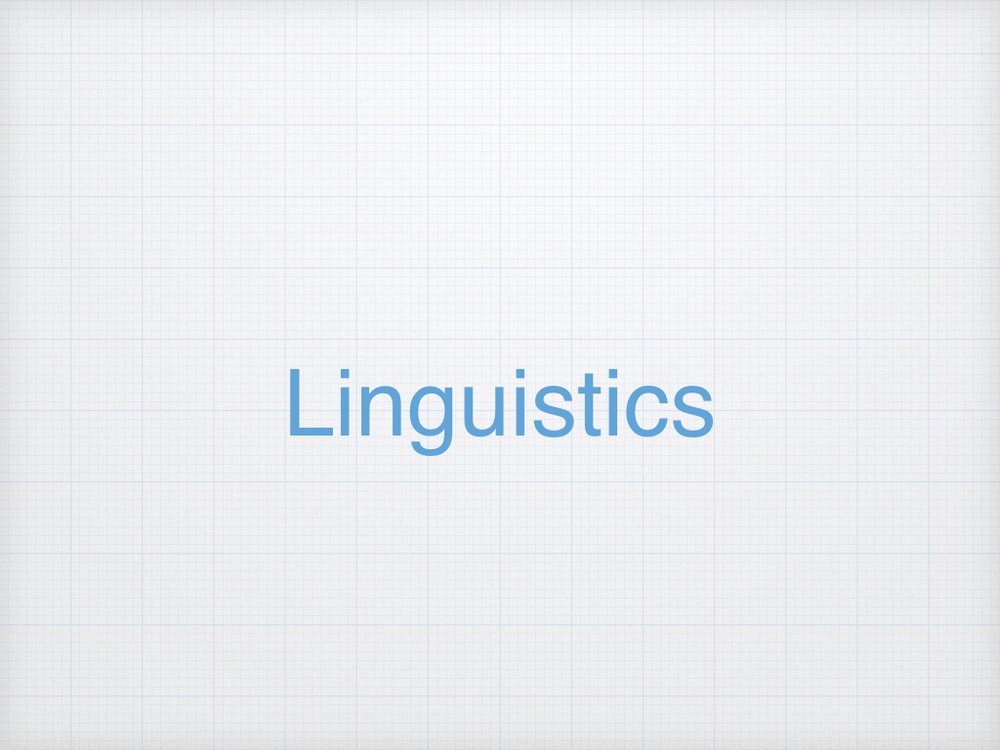3つのクラス
言語はさまざまな観点から見ても多様である. 例えば, 日本語とフランス語, ドイツ語と韓国語など, 個別言語間の多様性や, 個人内で乳幼児期と成人以降に起こる多様性など様々である. Fujita (2003) はこの多様性を「発生」という観点から次の3つに分類した.
(1)
A Microgenesis
言語知識が生み出す言語表現の多様性
B Ontogenesis
個人の発達過程で生じる言語知識の多様性
C Phylogenesis
言語の起源, 通時的変化とその結果としての言語知識の共時的多様性
(Fujita, 2003, pp. 108-109)
見ると分かるがこの分類に当たって使われている用語は, 生物学的な用語であることが非常に興味深い. そもそもの論文の趣旨が生物言語学についてであることもあるが, これらの内容を真に理解するためには生物学の知識が不可欠になる. OntogenesisとPhylogenesisは, 用語とOntogeny(個体発生)とPhylogeny(系統発生)からきている言葉であると容易に見当がつくが, Microgenesisはさらにユニークな発想であるといえる. 本質的な理解をするためにも生物学の勉強を進めていきたい.
参考文献
- 藤田耕司. (2003). 生物言語学の展開-生成文法から見た言語発生の諸問題. Viva origino, 31(2), 104-121.