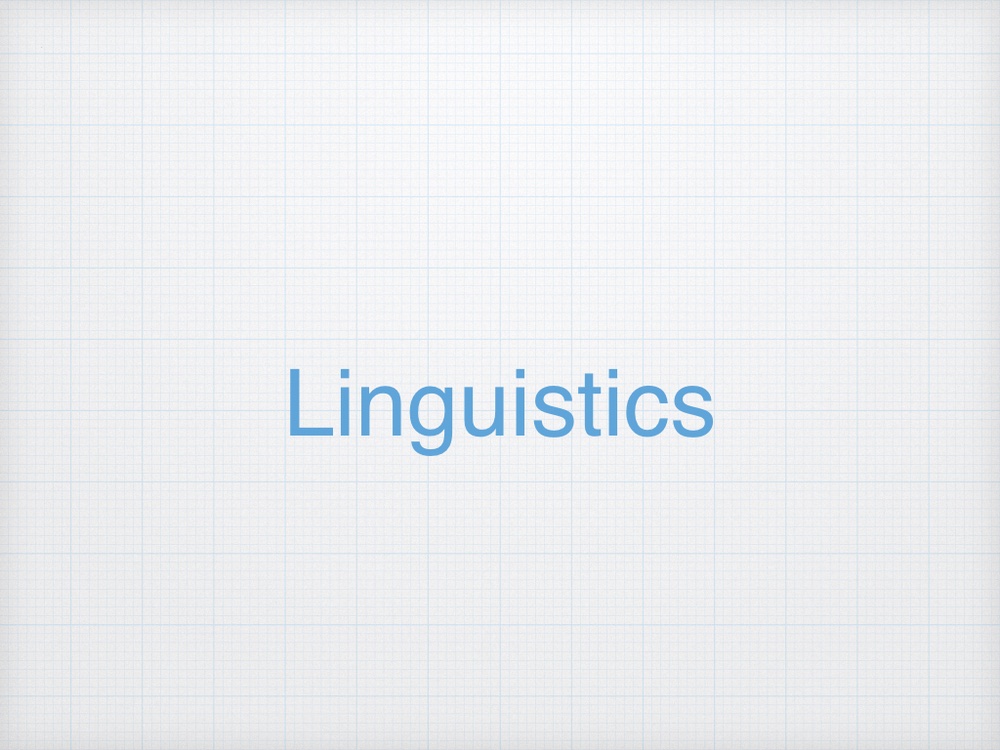変異体は孤独である. 2
以前の投稿で, 孤独なミュータントの問題(Fujita, 2016)という内容を扱った.
これを別の表現で説明した論文としてShukla (2005)が存在するので見てみたい.
Notice that such a view of the innovation of Merge has a direct fitness benefit at the individual level. It is clear that for efficient communication, both the speaker and the listener must have appropriate language skills; there needs to be both a coder and a decoder. That is, if language evolved primarily for communication, it would require concomitant evolutionary changes for there to be both a speech (or sign language) producer as well as receiver.
(Shukla, 2005, p. 123)
併合の革新に関するこのような見解が、個体レベルで直接的な適応度上の利益を持つことに注意されたい。効率的なコミュニケーションのためには、話し手と聞き手の両方が適切な言語スキルを持っていなければならないことは明らかである。コード化する者と解読する者の両方が必要である。つまり、もし言語が主としてコミュニケーションのために進化したのであれば、音声(または手話)の生成者と受信者の両方が存在するために、付随する進化的変化が必要となるだろう。 (Gemini 訳)
とても端的にまとめられていて, 非常にわかりやすい表現である. なおかつ, ここでおさえたいのが“it would require concomitant evolutionary changes”という表現である. 付随する進化的変化が求められるということは, それ単体の進化を仮定する場合よりもより複雑なシナリオになることは間違いなく, それは言い換えるならば, 進化的な実現の可能性を否応なく下げることになるだろう. もちろん可能性が下がったからといってゼロではないため, 進化のつぎはぎが最終的にどういったストーリーだったかは再考の余地があるが, あくまでシンプルな理論を活用するならば, やはり言語は思考のためのツールであると考えた方がシナリオの複雑性を下げることができる.
参考文献
- Shukla, M. (2005). Language from a biological perspective. Journal of Biosciences, 30(1), 119-127.
- 藤田耕司. (2016). 生成文法と複雑系言語進化. 計測と制御, 53(9), 862-864.