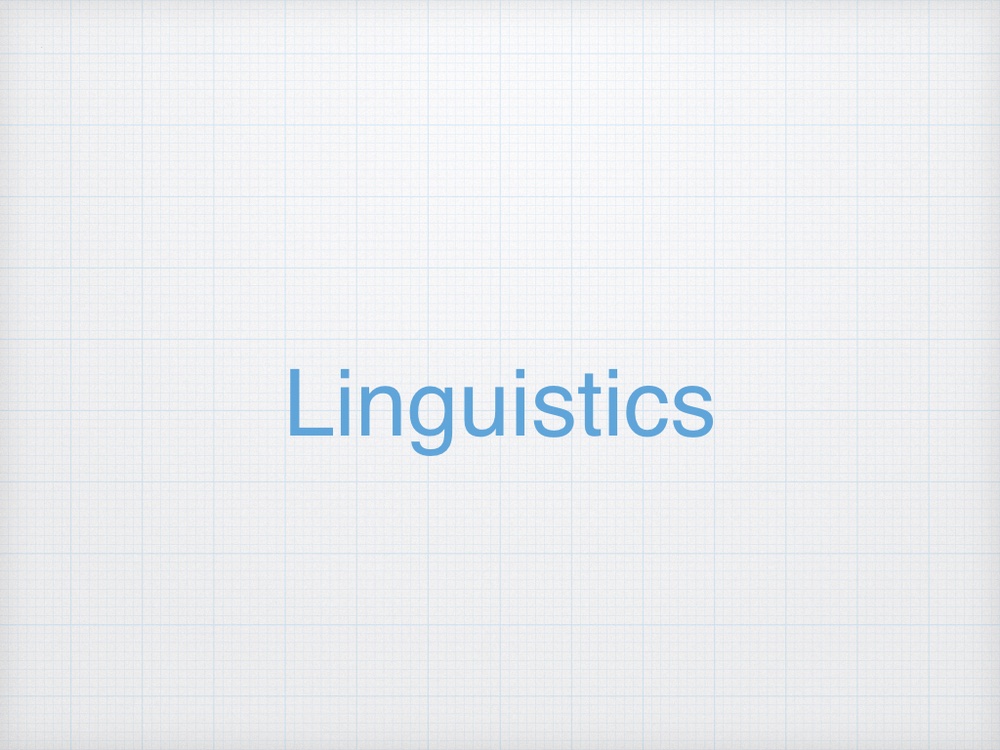分散形態論の基本方針
以前の投稿ではDistributed Morphology(分散形態論)についてまとめた.
今回は, その基本的な方針となる2つの主要な主義(tenet)について見ていく.
Distributed Morphology (DM) is a framework in theoretical morphology, characterized by two core tenets: (i) that the internal hierarchical structure of words is, in the first instance, syntactic (complex words are derived syntactically), and (ii) that the syntax operates on abstract morphemes, defined in terms of morphosyntactic features, and that the spell-out (realization, exponence) of these abstract morphemes occurs after the syntax.
(Bobaljik, 2017)
分散形態論(Distributed Morphology, DM)は理論形態論における一つのフレームワークであり, 次の2つの核となる信条によって特徴づけられる. (i) 語の内部階層構造は, 第一に統語的である(すなわち, 複合語は統語的に派生する)ということ. (ii) 統語論は, 形態統語素性の観点から定義される抽象的な形態素に作用し, これらの抽象的な形態素の具現化spell-out (realization, exponence)は統語部門の後で行われるということ.
(Gemini訳)
この2つの主義を見ると明確に感じるのは, 明らかに生成文法のような統語論と相性が良いということである.
語の内部構造自体にも, 階層的な構造を想定し, なおかつ明確に統語的であると述べている.
加えて, 形態素の具現化は, 統語部門の後で行われるということは具体的に目に見える形は別物であり, 裏側に複雑な演算処理が走っていると考えることができる.
こういった点を見ていると生成文法の研究者が時折Distributed Morphologyに触れるのも理解できる.
参考文献
- Bobaljik, J. D. (2017). Distributed morphology. In Oxford research encyclopedia of linguistics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199384655.013.131