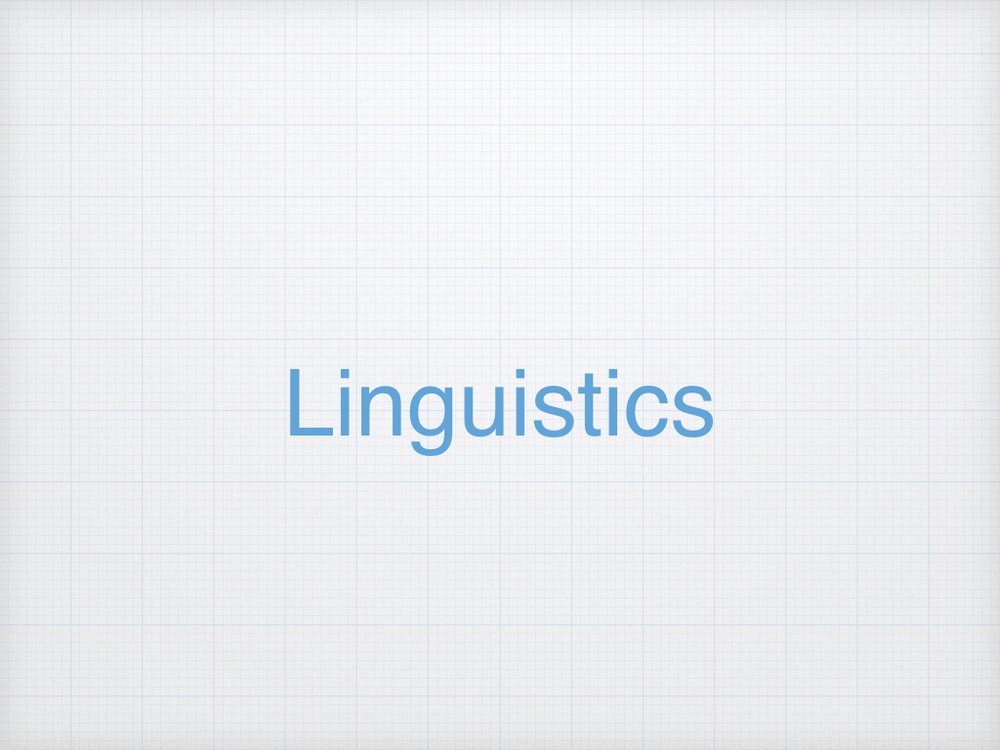重複と進化
人の言語能力の起源というものは未だ研究の途上にあり, どのように発現したのかは未だ謎が多い.
Shukla (2005) は大野 乾の “duplicate-and-evolve” (重複と進化) の概念を用いながら, 言語が発達した可能性を提示している.
「重複と進化」とは, まず既存の遺伝子や機能単位が「重複」してコピーが作られ, その後に重複したコピーの一方が元の機能的制約から解放されて自由に「進化」し, 新たな機能を獲得するというものである.
このメカニズムによって, 航法(ナビゲーション)などの言語以外の目的で存在していた「再帰的な処理を行う認知モジュール」が脳内で重複し, その結果生まれた新しいモジュールが, 意味や概念を扱うシステムのために転用され, 階層的・再帰的に思考を組み立てる能力へと発達したという仮説である.
大野 乾の “duplicate-and-evolve” (重複と進化) の概念を今回初めて知り, 門外漢の分野ではあるが非常に興味深い概念であるように感じた. さらに, このアイデアは言語の生物進化だけでなく文化進化でも応用ができるような非常に根幹的な概念である. 今度改めてじっくりと学んでみたい.
参考文献
- Shukla, M. (2005). Language from a biological perspective. Journal of Biosciences, 30(1), 119-127.