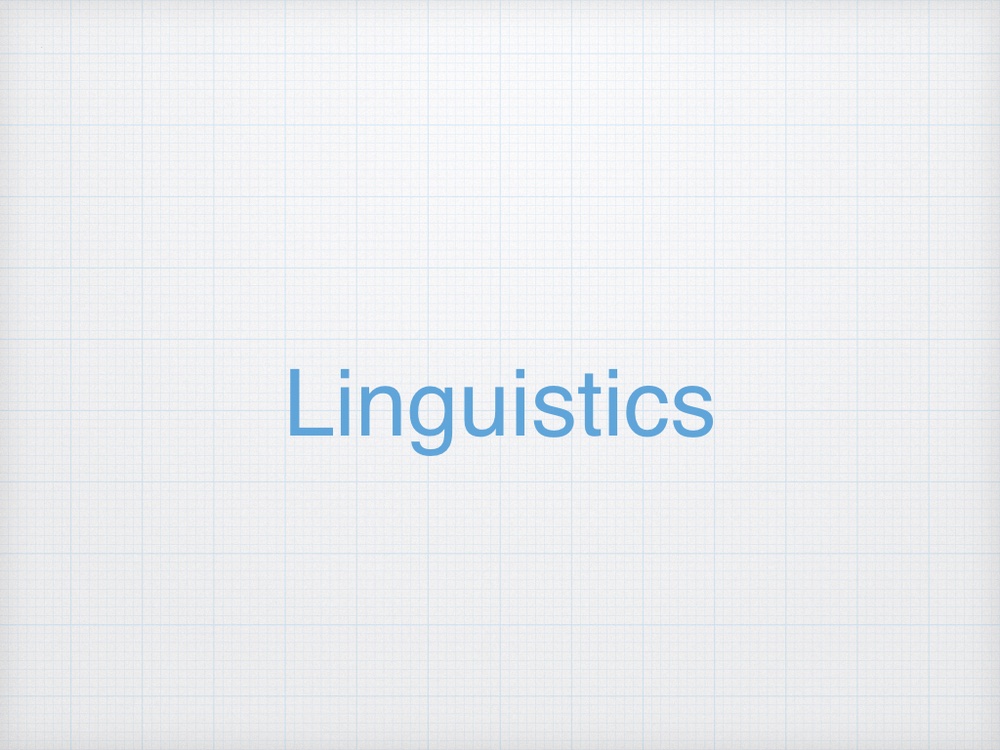言語の単位の恣意性
言語の研究をする際, 様々な単位を用いることがある. 例えば, 音声学においてはフットやモーラ, 韻律構造といった単位が用いられる.
しかし, これらの単位に関してMiyakoda (2018) は, 重要な指摘をしている.
言語研究で扱う単位の多くは,直接的にその実在性を証明することが困難であり,言語運用において観察される現象をもとに,「こういう単位を認めることでこの現象を正しくとらえることができるのではないだろうか」といった間接的なアプローチしかとることができない場合が多い.そういった意味では,ある言語単位の妥当性を見極めることは重要でありつつも.極めて困難な作業であるともいえる.
(Miyakoda, 2018)
この指摘は, 言語研究を進める上で常に意識すべき点である. 以前の投稿でも述べたが, 言語に対して抽象的な構造を仮定することで, 直接観察可能なもの以上の理論化が可能となり, その自由度が飛躍的に向上する. 一方で, その理論が観察可能なデータから逸脱しないよう細心の注意を払う必要がある.
この, 理論上想定されるものと実際に観察可能なものの間を行き来し, それぞれの妥当性を検証しながら進める手法は, 物理学の研究方法に類似している.
参考文献
- 西原, 哲雄 (編). (2018). 言語の構造と分析―統語論、音声学・音韻論、形態論― (言語研究と言語学の進展シリーズ1). 株式会社 開拓社.