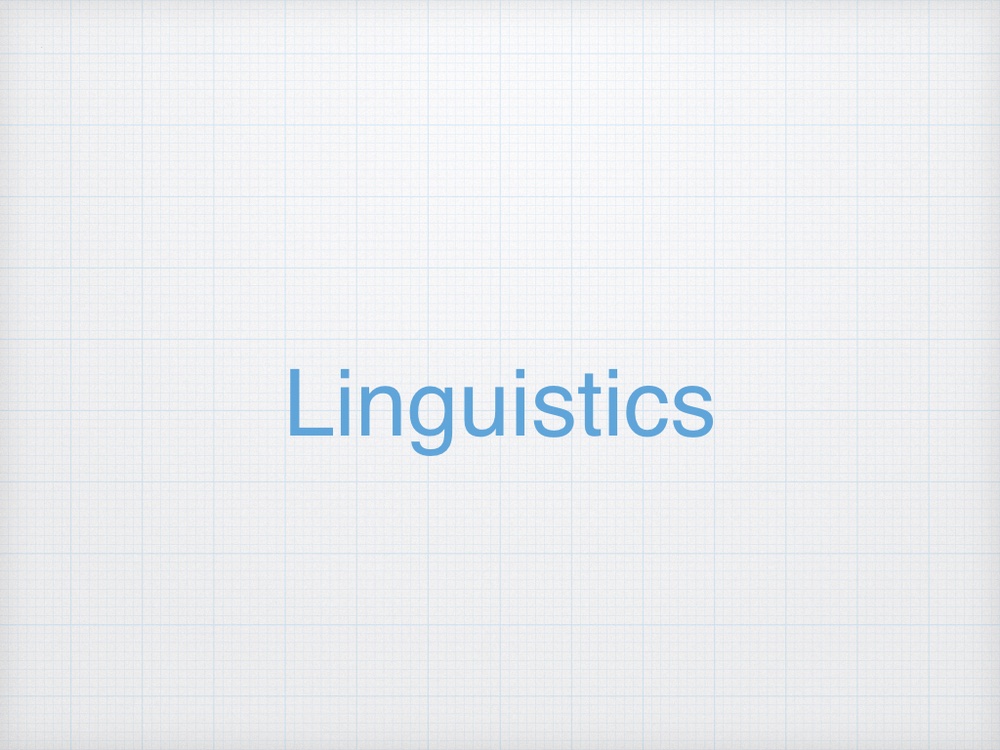生成文法では, 人の言語能力は普遍的なものであると仮定している.
他方で実際の言語を観察してみると, 日本語や英語, フランス語, そのほか様々な言語において, 普遍的と考えられる部分もあれば, 非常に多様でバリエーションに富む部分も存在している.
生成文法が人の言語能力を普遍的なものであると仮定する以上, この多様でバリエーションに富む部分に対しての説明を当然求められる.
過去に生物学で似たような現象があった. Fujita (2003) を引用しよう.
例えば Charles Darwin は生物種の多様性, 生物世界における可変性に注目し, それを(主に)自然選択という原理を通じて理解することを提案した. ほぼ同じ時代に, Gregor Mendel はむしろ一様性や保存性に注目し, 世代を渡って形質が受け継がれるという現象を遺伝因子の存在, とりわけその粒子性に基づいて解読してみせた. この変化対保存, 多様対一様という一見相容れない二つの現象の一方ずつに関わるはずであった研究パラダイム-Darwin 進化論と Mendel 遺伝学-は, 20 世紀初頭, Mendel 遺伝則の再発見に続いて起きた「現代の統合」(ModernSynthesis, 総合説進化論)によって矛盾なくまとめ上げられるに到る.
(Fujita, 2003, p. 107)
ここで述べられている比喩は非常に示唆に富むだろう.
過去の生物学では, 生物の多様性と一様性という相反する性質のものを一つの理論に統合した歴史がある.
現代の言語学においても必要となるのは, この発想である.
つまり, 言語の多様性と一様性を両立させるためのファクターXが存在すると仮定し, そのXを突き止めることこそ重要な作業の一つと言える.
参考文献
- 藤田耕司. (2003). 生物言語学の展開-生成文法から見た言語発生の諸問題. Viva origino, 31(2), 104-121.