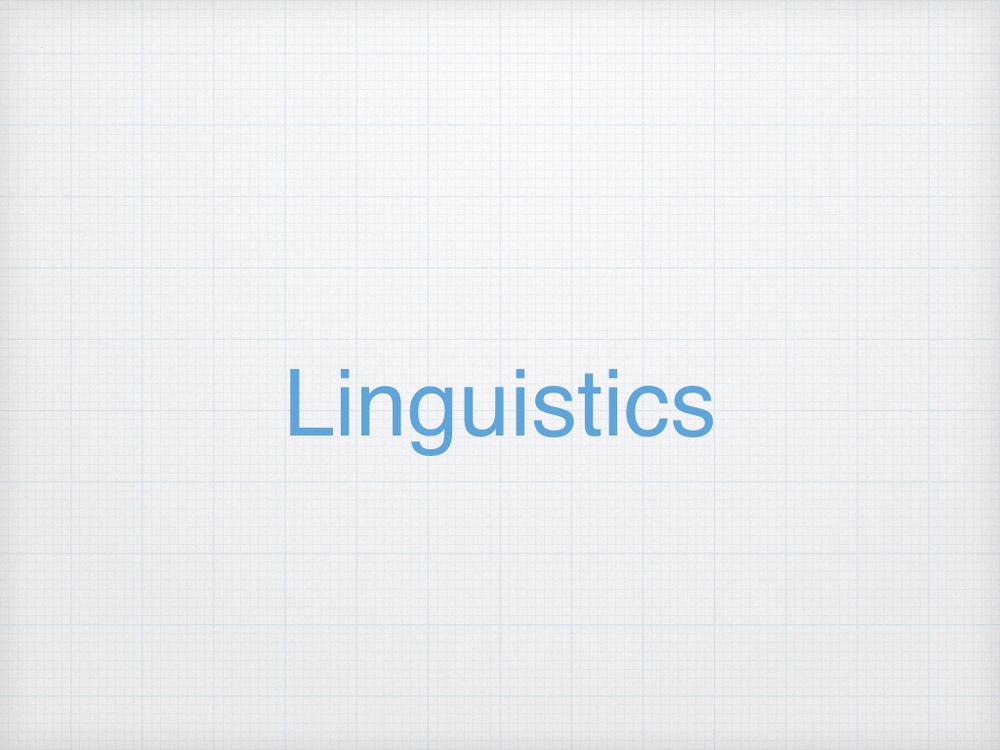Coordinationを考える
- (a) 私はりんごとバナナが好きだ.
この文では, 「りんご」という名詞と「バナナ」という名詞が「と」によって接続されており, 「りんご」と「バナナ」の両方が好きであるという意味を構成している.
このとき, 接続された要素は生成文法の観点から見ると, 同じθ-role(シータ役割)が付与される.
さらに重要なのは, 「りんご」と「バナナ」の語順を入れ替えても, 文全体の意味が保持される点である. 以下の文を見てみよう.
- (b) 私はバナナとりんごが好きだ.
この文1.(b)は, 文1.(a)と同様に, 「りんご」と「バナナ」の両方が好きであるという解釈を許す.
したがって, 等位接続構造は意味的に対称性を持つことができると言える.
一方で, 音声言語においては, 文を外在化する際に, 線形の音素列として出力する必要がある.
そのため, 必ず一方の要素が他方に先行して出力され, 音韻的には非対称性が生じる.
例えば, 文1.(a)では「りんご」が「バナナ」に先行して外在化される.
このため, 意味的には対称であっても, 音韻的には「りんご」が先に出力されるという点で非対称性を持つ.
このように, 等位構造は意味的対称性と音韻的非対称性という二つの異なるレベルの構造を同時に包含している.
参考文献
- 浅田裕子. (2019). 日本手話における等位接続の特性 (1) 等位接続の同時性における非対称分析. 手話学研究, 28(1), 20-30.