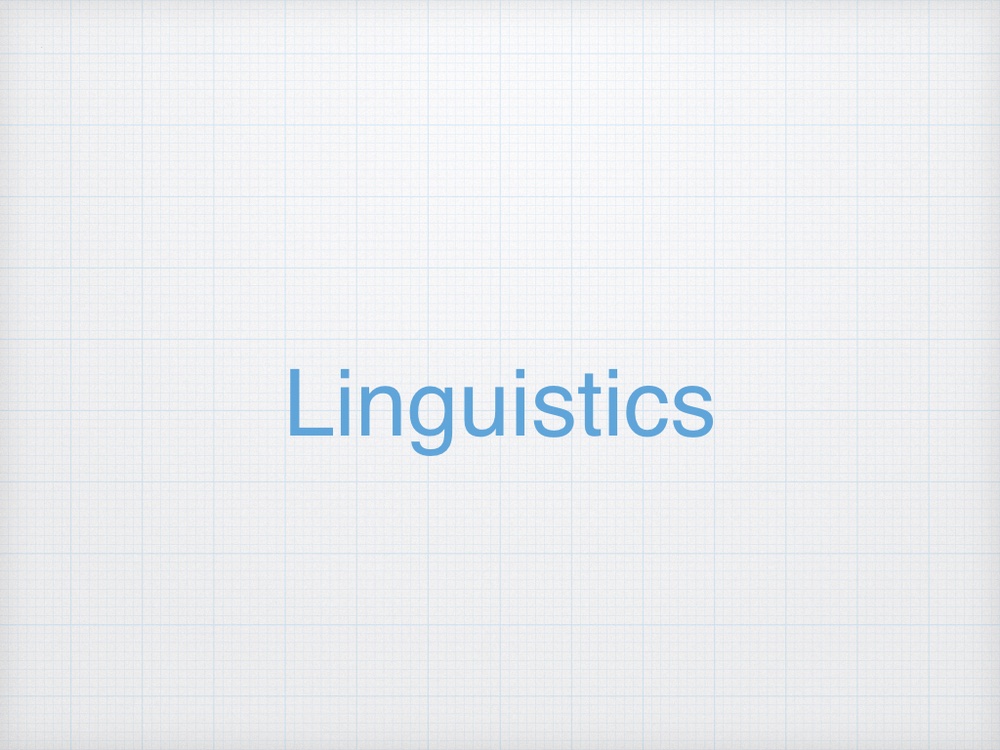LGBからSMTへ
生成文法の発展の歴史は度々投稿している. その中でも統率・束縛理論 (Lectures on Government and Binding, 以下LGB) からミニマリスト・プログラムにおける強い極小主義のテーゼ (The Strong Minimalist Thesis, 以下SMT) への移行は, 非常に大きな転換点であった. Nawata (2011) はこの変化を「大きなUG」から「小さなUG」への変容と表現しているが, 非常に秀逸な表現であるように思える.
これは言い換えれば, これまでの個別言語の可変部分を説明する言語固有のパラメターと, 全ての言語に共通する普遍的な原理 (Principle) によって言語現象を捉えるのではなく, 人間の言語能力の根幹をなす併合 (Merge) と, 計算の経済性などの一般的な原理 (いわゆる第三要因) に還元していくという, 方針のシフトを意味する.
そして, ここでNawata (2011) は非常に重要な指摘をしている.
注意しなければならないのは, これらの経済性原理が, 言語の領域固有性の外部に由来するという性質上, 言語的なパラメター化を受け付けないということである.
(Nawata, 2011, p. 73)
言語に固有の性質ではないということは, 言語の根幹能力をよりシンプルに捉えることができる一方で, それらを言語間の差異を説明するための「パラメター」として扱うことを不可能にすることも意味する. つまり, 同じ対象を分析するにしても, それまでのLGBでの発想方法を根本的に変える必要が出てくる.
この点は, いかにLGBからSMTへの移行が劇的なパラダイムシフトであったかを表している一例と言えよう.
参考文献
- Nawata, H. (2011). 極小主義における通時的パラメター変化に関する覚書 ―「言語変化の論理的問題」の解消に向けて―. 島根大学教育学部紀要(人文・社会科学), 45, 71-82.