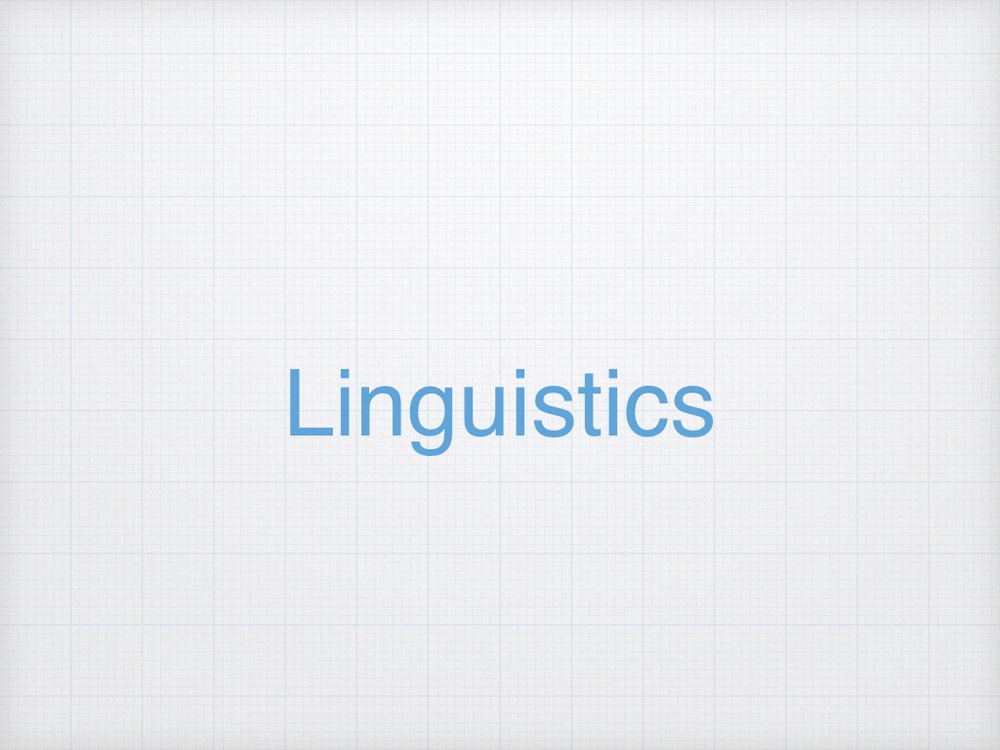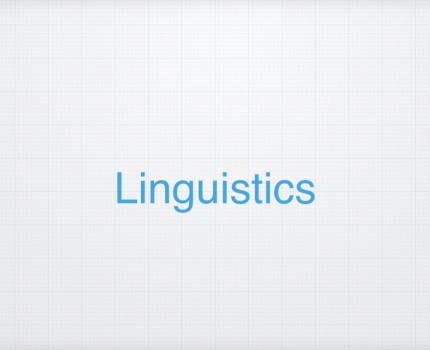以前の投稿で等位構造が様々なアプローチで分析されてきたことを見てきた. 今回はZhang(2024)に基づき, それぞれの分析方法の問題点をまとめる.
- 対称的姉妹関係分析は, 第一等位接続要素が第二等位接続要素を非対称的に
c-統御 (c-command)することを示す経験的事実(束縛関係, 否定極性項目の認可, 範疇選択)と矛盾する. - 指定部-補部分析は非対称性を捉えられるが, 範疇を持たない等位接続詞がどのようにして句全体の範疇を決定するのか(通常は指定部からの素性浸透というアドホックな仮定に頼る), また, 構造に特化した機能範疇を仮定する点で問題がある.
- 付加分析も, 構造特有の機能範疇
BPを仮定し, この句が付加部としてしか機能しない点で他の句と異なり, 理論的に特殊である. - 多重支配分析は, 構造に特化した併合操作や複雑な線形化規則を必要とし, より単純な二次元的アプローチで説明可能であれば, その複雑さは正当化されない.
- 姉妹移動分析は, 等位接続詞が等位接続要素のペアを選択するという構造特有の操作を仮定し, またラベル付け理論に関して不自然な予測を生む.
これらを見ると明らかであるが, それぞれの分析において一長一短があることがわかる. それはつまり, 今の理論では包括的な説明ができておらず, この理論に改善の余地がある事は明確である. この課題を埋めていくのが我々の仕事になっていくであろう.
参考文献
Zhang, N. (2024). Coordinators and modification markers as categoryless functional elements. Nordlyd, 48(1), 39-57.