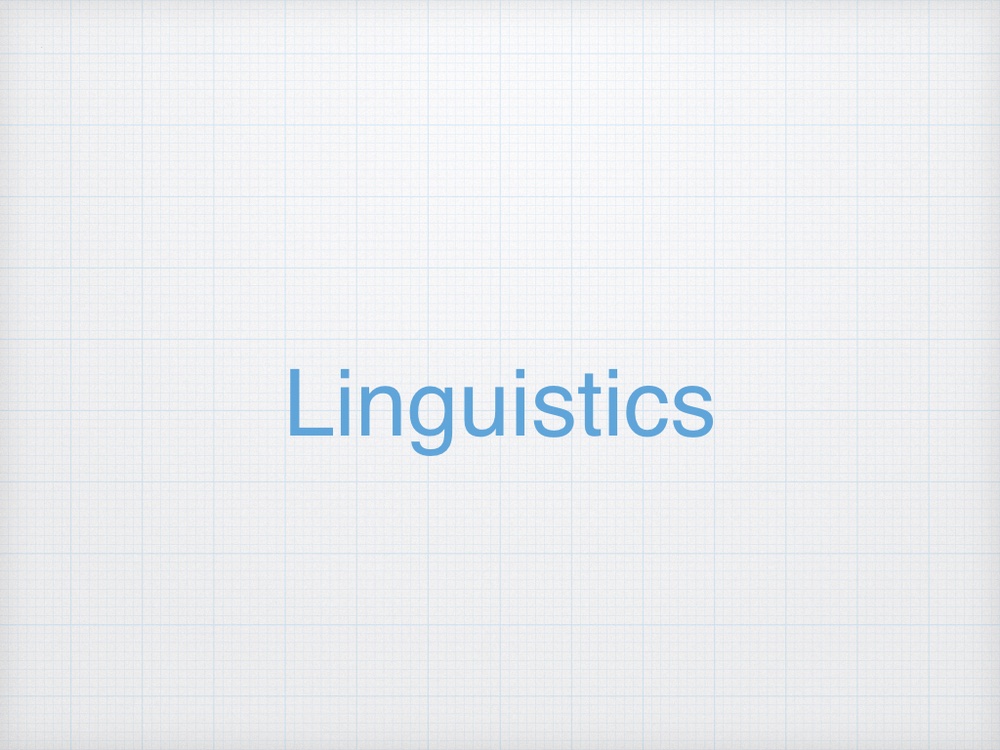分析の標準を策定して良いのか?
統語論の代表格である生成文法では, 基本的に標準アメリカ英語を分析の対象にすることが多い. しかし, これはなぜなのだろうか?
また, これを分析の標準として良いのだろうか?
Adger & Trousdale (2007) はこの状況に疑問を呈する.
ここでは, Adger & Trousdale (2007)に従い標準アメリカ英語が分析の標準になっている理由をまとめながらみてみたい.
- 標準(アメリカ)英語 (Standard (American) English)は, 英語全体としては理論的に重要な統語変異(例:wh疑問文, 上昇構文, 統制構文, 受動態, 基本的な節構造など)は少なく, これらの現象が理論構築の中核データを形成するという仮定が存在する.
- 標準英語は, 異なる話者の特定の言語を理想化した, 合理的な研究対象であるという暗黙の仮定が存在した. Chomsky (1965) の「研究対象の理想化は正当である」という議論に従い, 研究者はこの理想化に挑戦するような変異を無視する傾向があった.
- 研究者(多くは標準英語の教養ある話者)自身の直感(内省)を利用できる標準英語の研究は, 方言変種の研究よりも単純に容易である. これにより, フィールドワークや方言データの収集に伴う複雑さへの対処が不要となり, 時間とエネルギーを節約できる.
Adger & Trousdale (2007)を参考に要約
個人的に注目したいのは, 3の利便性である. 私も東京出身のため, 無意識のうちに標準語話者の便益を享受しているように思うが, これはどうしてもバイアスがかかる. もちろん, 2にあるように理想化を認める生成文法なので, それでも良いのかもしれないが, 他方で, 普遍性を考慮する生成文法だからこそ様々な方言等も考慮しなければならないと改めて感じる.
Adger, D., & Trousdale, G. (2007). Variation in English syntax: theoretical implications. English Language & Linguistics, 11(2), 261-278.