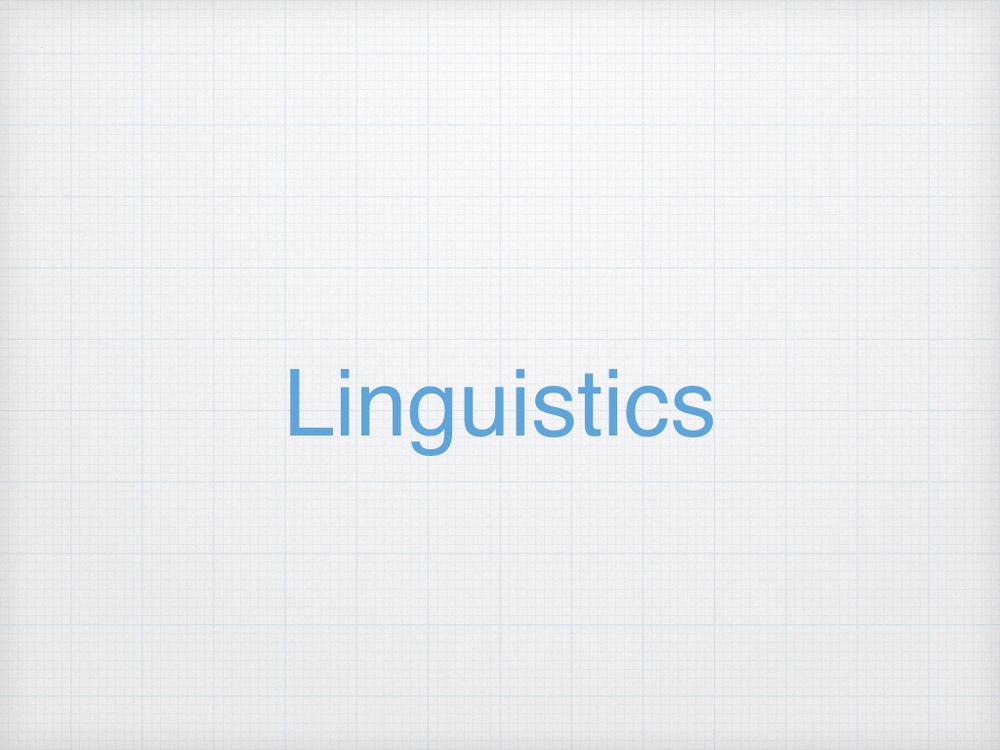言語の計算機構
生成文法の理論はミニマリストプログラム以前と以降で, 大きく傾向が異なる. この傾向が顕著に現れ始めた論文の一つが Hauser, Chomsky, and Fitch (2002) である. この論文では, ヒト固有の言語能力を the Faculty of Language in the Narrow sense (FLN) という表現で説明し, 日本語では「狭義の言語能力(FLN)」というように訳されることが多い.
Boeckx (2013) はこの FLN を Hauser, Chomsky, and Fitch (2002) の内容を引用しながら次のようにまとめる.
Although Merge is not explicitly mentioned in Hauser, Chomsky, and Fitch (2002), it figures prominently in their claim that the Faculty of Language in the Narrow sense (FLN)—that which is specific to humans—likely consists solely of the ability to build syntactic structures recursively and map these to the systems of ‘sound/sign’ and ‘meaning.’ It is not hard to recognize Merge in statements like “the core computational mechanisms of recursion as they appear in narrow syntax and the mappings to the interfaces” (p. 1573, column 2–3).
Hauser, Chomsky, and Fitch(2002)において、Mergeは明示的には言及されていないものの、人間に固有とされる「狭義の言語能力(Faculty of Language in the Narrow sense, FLN)」が、再帰的に統語構造を構築し、それを「音/記号」と「意味」のシステムへと写像する能力のみによって構成されている可能性が高いという彼らの主張において、Mergeは中心的な役割を果たしている。その主張の中の「狭義の統語における再帰の中核的計算機構と、それをインターフェースへと写像する機構」(p. 1573, column 2–3)といった記述の中に、Mergeの存在を見出すことは難しくない。
ChatGPT 訳
個人的に特筆したい表現が “the core computational mechanisms” という部分である. 言語能力の中核を成すのは Merge であり, それは計算機構の中核であるという発想は, 一般の人にはなかなか理解してもらえないかもしれないが, 非常に興味深い発想である.
参考文献
- Boeckx, C. (2013). Merge: biolinguistic considerations. English Linguistics, 30(2), 463-484.