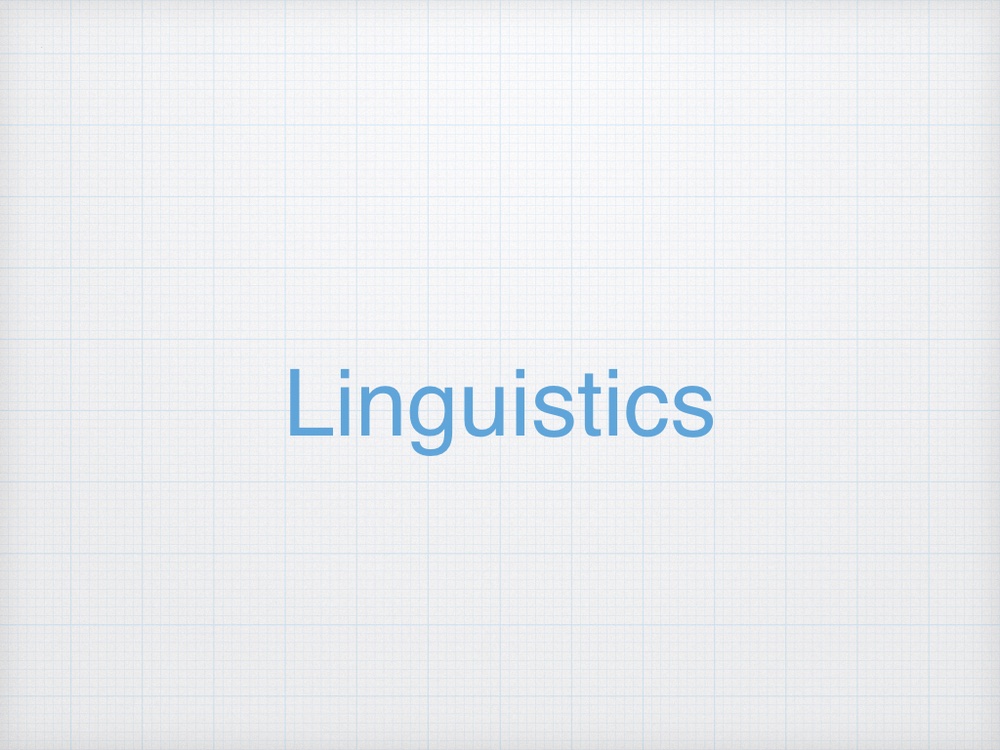言語を考える上で
研究に従事する限り, 論理的な思考を求められるが, それはすなわち適切なストーリーを描くことであるとも言える. 現在の理論言語学, とりわけ生成文法においては, ヒトの言語を統語構造を用いて意味と音を対応させるシステムと捉えることが主流である (Fujita, 2012). すなわち, 音, 意味, 統語構造の三つのモジュールを常に意識しながら理論研究を進める必要がある.
これら三つのシステムは, 相互に独立していながらも接続された構造として機能しており, それを可能にするインターフェイスの存在が前提とされる. したがって, 我々は三つのモジュールそれ自体だけでなく, それらを接続するインターフェイスにも注目しなければならない.
この視点を踏まえて言語の進化を考察する場合, 中枢神経系において音, 意味, 統語構造を統合・接続する神経メカニズムがいかに獲得されたのかという問いが浮上する. 仮に言語をコミュニケーションの道具と仮定するならば, 初期段階では単純な発声や事象の表象が先行し, その後に統語構造を操作する抽象的能力が急速に発達することで, より豊かな意味伝達が可能になったと考えられる. このような適応的変化の過程を明らかにすることは, 言語進化の解明に向けた鍵となるであろう.
参考文献
- 藤田, 耕司, 岡ノ谷, 一夫, 浅田, 稔, 池内, 正幸, 岩本, 和也, 内田, 亮子, 笠井, 清登, 笹原, 和俊, 東条, 敏, 野澤, 元, 橋本, 敬, 山内, 肇, 遊佐, 典昭, & 吉川, 雄一郎. (2012). 進化言語学の構築: 新しい人間科学を目指して. ひつじ書房. https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB08778820