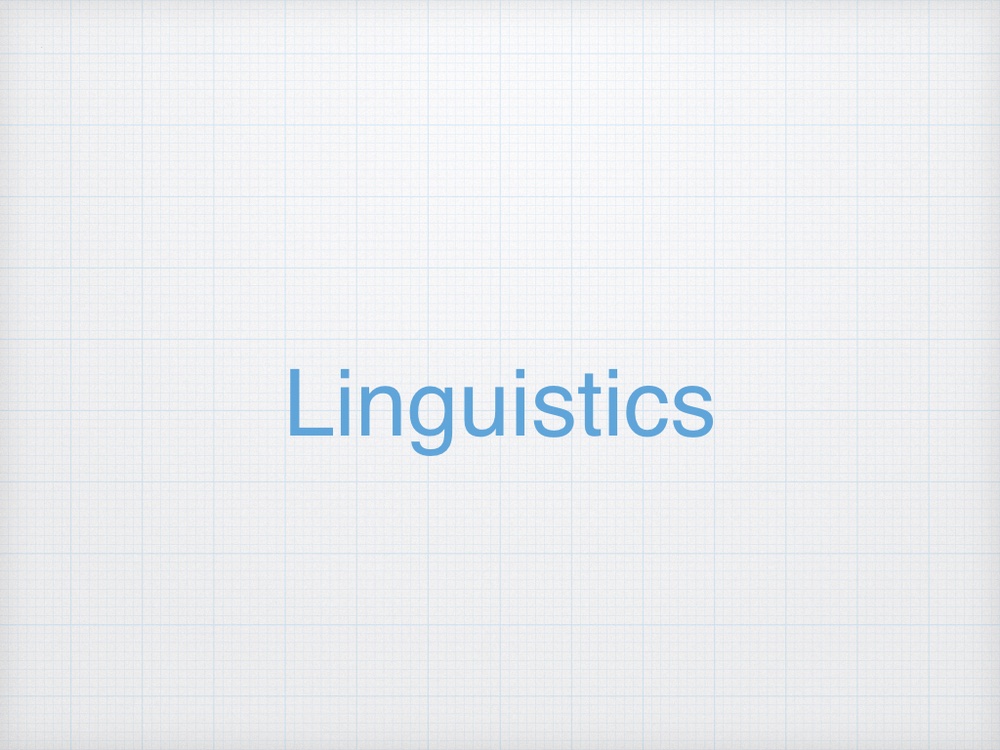移動できる方がイレギュラーか.
生成文法では(様々な形に変えつつも)構成素は移動もしくはコピーが行われていると想定する. そしてその際, 移動ができないような事例に対しては, そこに説明を与え, 理論的な整合性を保っている.
他方で, Progovac (2015) はむしろ逆の発想をして, この現象に対する説明を試みている.
However, the approach explored here stands this argument on its head and shows that subjecting syntax to a gradualist evolutionary scenario can in fact explain the existence of islandhood effects. In this view, Subjacency is not a principle of syntax, or a principle of any kind, but rather just an epiphenomenon of evolutionary tinkering. Subjacency or islandhood can be seen as the default, primary state of language, due to the evolutionary beginnings of language which had no Move. This default state can be overridden in certain, evolutionarily novel, fancy constructions, such as hierarchical CPs.
(Progovac, 2015, p. 31)
しかし, ここで検討されているアプローチはこの議論を逆転させ, 統語を段階的な進化シナリオに従わせることによって, 島効果の存在を実際に説明できることを示している. この見解によれば, 「下接性(Subjacency)」は統語の原理でもなければ, いかなる種類の原理でもなく, むしろ進化的な工夫(evolutionary tinkering)の副産物(epiphenomenon)にすぎない. 下接性や島現象は, そもそも「移動(Move)」を持たなかった言語の進化的起源に由来する, 言語のデフォルトで一次的な状態と見なすことができる. このデフォルト状態は, 階層的なCPのような, 進化的に新しく洗練された構文構造においては覆されることがある.
(ChatGPT 訳)
この主張は非常に面白い. そもそも人間の言語は他の動物と同じく平坦な線形の構造を持つものが原始的に存在しており, それが階層的なCPなどの登場によって, 後続的に移動などの現象が可能になったと主張している. 別の言い方をすれば, 移動ができない状態こそ人間言語の原始的な状態であり, 移動ができる今の形の方が, 進化の過程で発展した言語表現であると考えられるということだ. これは理論構築の際に発想の転換を意味し, なおかつ, 移動現象に対しての新たな示唆を提供するような主張であると言える.
とりわけ私は, 等位構造の発達に興味を持っているが, この発想にのっとれば, 等位構造においても, 別の発想方法が可能になるかもしれない.
参考文献
- Progovac, L. (2015). Evolutionary syntax. Oxford University Press.