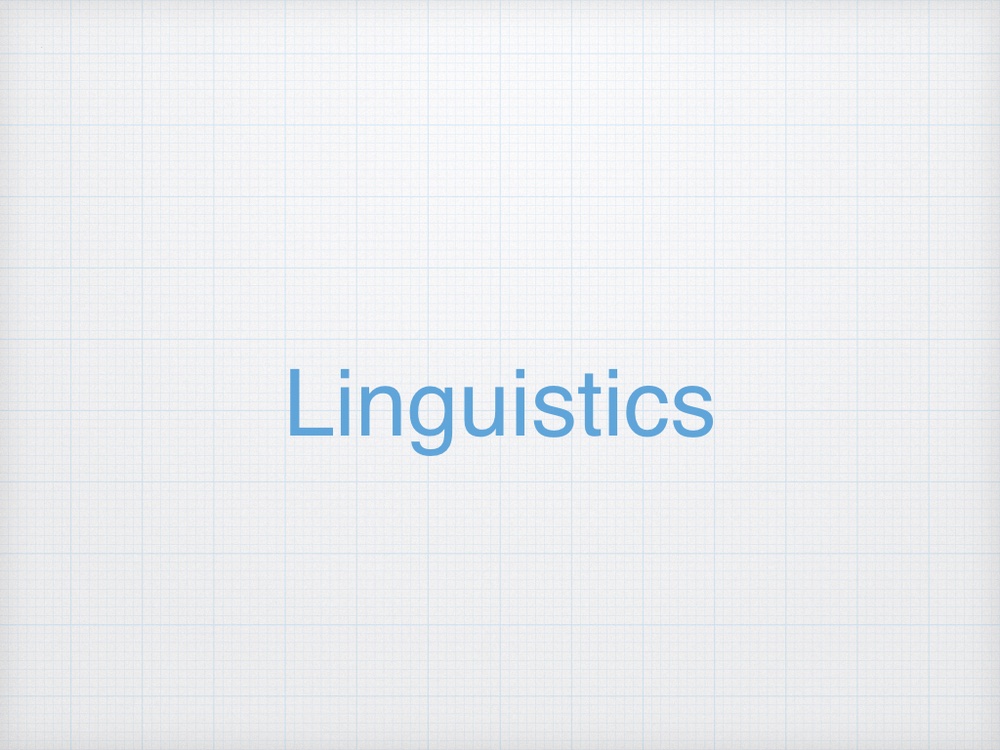第3要因への移行の問題点
現在のミニマリストプログラムの最大の特徴の一つは普遍文法として, 言語の特徴として知られた性質を言語以外の自然世界の一般的な方式から導き出そうとする第三要因の仮定である. これにより, 言語がどうなっているのかだけではなく, なぜそうなっているのかという説明的妥当性を超えた探求を目指すことが可能になった. 他方で, この方針に則ったがゆえに, 従来にはなかった問題点も発生している. Fujita (2018) はその点を指摘しており, またその指摘は我々が常に研究をする際に気をつけなければならない点であると考える.
現状、この第三要因に起因するとされる言語の設計原理が「最小演算 (minimal computation)」「演算効率 (computational efficiency)」「最小探索 (minimal search)」といった抽象的な概念で語られ厳密に定式化されてはいないという点、またそのような概念と関係づけられそうなものであればどのような制約も認められてしまうという点、さらに、これらは果たして一般的自然法則といえるほど自然世界にあまねく作用しているものなのか、かなり言語に特定的な面が残っており単に自然法則に言及するだけでは不十分なのではないかといった点が問題として残るものの、今後の研究の方向性としては妥当なものだと考えられる。
(Fujita, 2018, p. 109)
この引用を端的にまとめれば, 概念が厳密でないがゆえにあらゆる制約が認められてしまうという欠点と, 自然法則という便利な仮定をするがゆえに, その仮定の検討が十分行われないような議論が進んでしまう可能性を指摘していると考えられる.
言い換えるならば, 我々がミニマリストプログラムに則って研究を行っていく際, この厳密性や自然法則が本当に妥当なものであるかといったところに, 目を配らせながら研究を進めていく必要があるということであろう.
参考文献
- 遊佐典昭(編),杉崎鉱司,小野 創,藤田耕司,田中伸一,池内正幸,谷 明信,尾崎久男,米倉 綽. (シリーズ監修 西原哲雄, 福田稔, 早瀬尚子, 谷口一美). (2018). 言語の獲得・進化・変化―心理言語学,進化言語学,歴史言語学 (言語研究と言語学の進展シリーズ3). 開拓社.