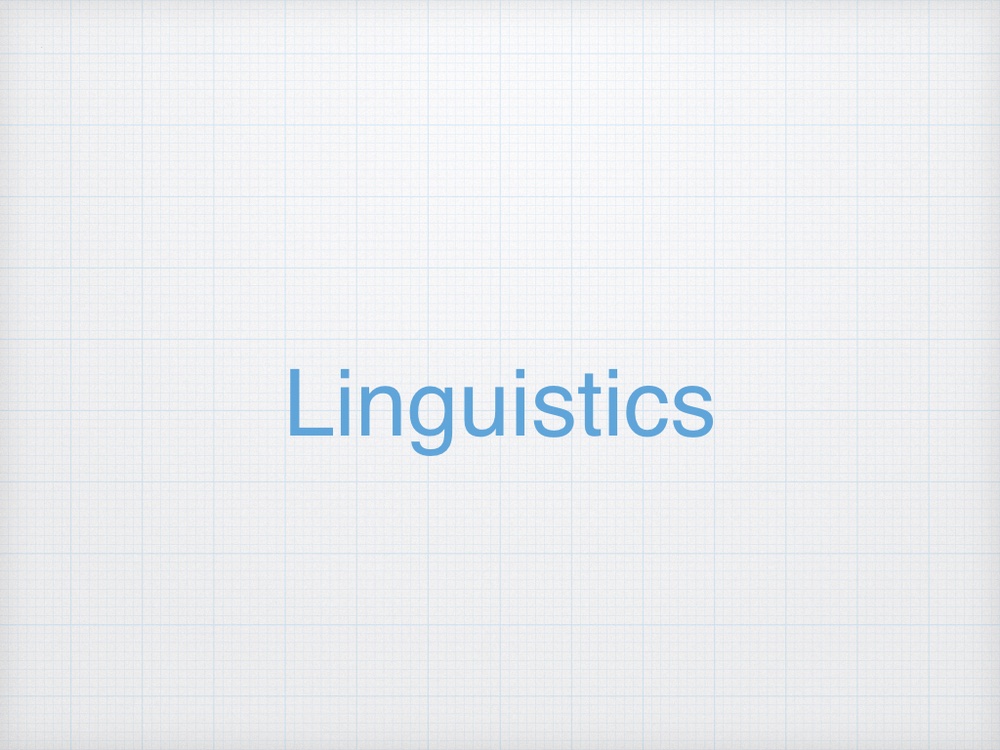どのように階層が組まれるか
以前の投稿で厳密階層仮説について見た. これは, 簡単に言えば韻律階層がどのような階層を持つか, そして, どのように互いが関係しているかをまとめた仮説である.
今回は, それが具体的にどのような制約を持って階層構造を組んでいるのかを見てみたい. Dohashi (2021)を引用する.
(48) 韻律階層の支配関係に課される制約
a. 層性(Layeredness)
韻律階層で下にあるべき要素が上の要素を支配してはならない.
例:韻律語が音調句を支配してはならない.
b. 主要部性(Headedness)
各韻律範疇は韻律階層で1つ下の階層の要素を必ず1つはその構成要素として持っていなければならない.
例:音調句は韻律語をその構成要素として持っていなければならない.
c. 包括性(Exhaustivity)
韻律範疇は2つ以上下の階層を直接支配してはならない.
例:音調句は韻律語を直接支配してはならない.
d. 非回帰性(Nonrecursivity)
韻律範疇は同じ韻律範疇を支配してはならない.
例:音韻句が音韻句を支配してはならない.
(Dohashi, 2021, p. 29)
これを見ると興味深いことに, 統語論で想定されているような制約と似たものが見受けられる. 例えば主要部性などは統語論にも見られる現象であり, この分野が統語論をベースに研究したがゆえに, このような制約が想定されているのか, それとも, そもそも人間の言語には本質的にこういった特徴が備わっているのか, といった観点で考えてみると, これらの類似性というのは捉え方が大きく異なってくるはずである. この特徴は非常に面白い.
参考文献
- 中村, 岸本, 秀樹, 毛利, 史生, & 中谷健太郎. 統語論と言語学諸分野とのインターフェイス.