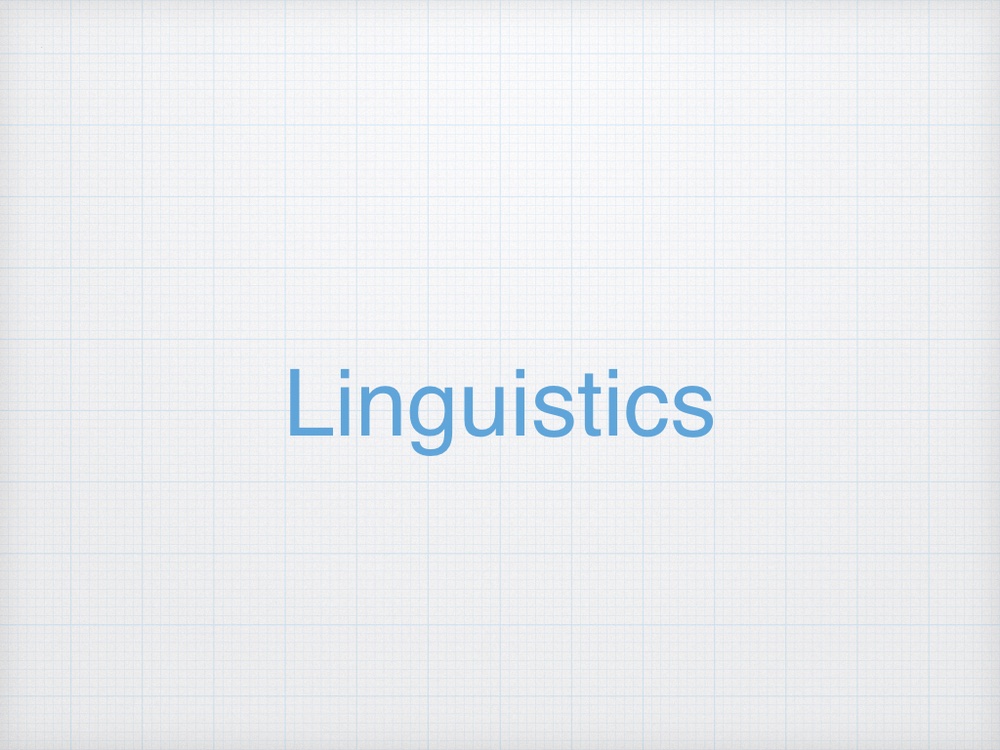誤分析
以前の投稿で, 人間は実は文法的な文でも, 普段接する頻度やその文の何の要素がどの品詞に属するかといった誤分析で文の意味がわからなくなってしまうことを見た.
これに対してImai et al. (2019)が非常にわかりやすい例を挙げている.
- Dogs I like don’t bite.
- Dogs dogs bite bite.
(Imai et al. 2019, p46)
この2つの文を見比べたとき, おそらく多くの人が文1の方は理解がしやすく, 文2の方は, 一見しただけでは理解しにくいと感じるであろう. しかし, 文1を理解しやすいと感じた人も, 落ち着いて文2を見れば, 実は文1も文2も品詞の観点からは同じ並びをしていることがわかる.
では, 何が違うかというと, 文には同一の要素が繰り返し表出しており, この観点で我々の処理に影響を与えていると考えられる. Imai et al. (2019)はこれを, I言語の問題ではなく, 統合解析の段階で解析不能になるという解析側の問題であると論じている.
また, さらにより複雑な例文として次の文章を挙げている. これがどういった意味になるのかは, ぜひ皆さんに考えてみていただきたい.
Oysters oysters oysters split split split
(Imai et al. 2019, p46)
参考文献
- 今井, 中島, 西山 & 外池. (2019). チョムスキーの言語理論: その出発点から最新理論まで.