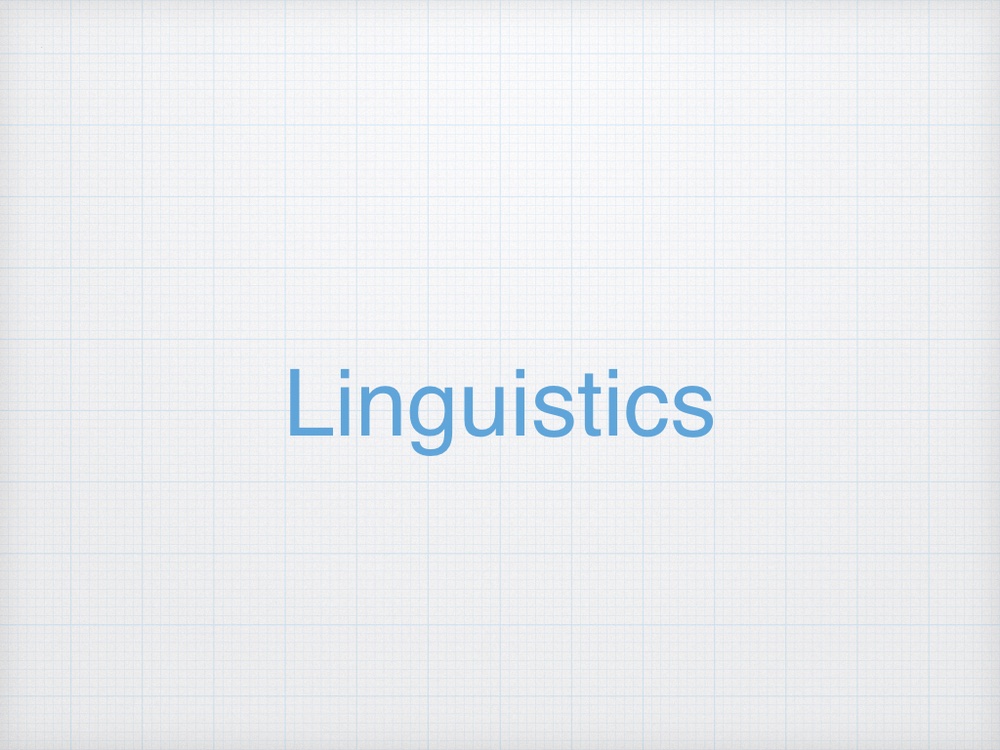等位構造をどのように分析するか
生成文法の研究トピックの一つに, Coordination Structure (等位構造) の解明が挙げられる. 以前の投稿でもまとめているが, 等位構造とは接続詞 (‘and’ や ‘or’) を用いて2つ以上の要素を結合し, 新たな句や文を形成する構造である. この等位構造は, 生成文法の中で理論化が非常に難しく, 長年大きな問題の1つとされてきた. 今回は, この等位構造に対する理論化において, 主要な二つの分析指針をまとめる.
等位構造に関するアプローチの二つの大きな方針は, 主に下記の二点である.
- Conjunction as a head (接続詞を句の主要部と見なす方針)
- Conjunction as non-head (接続詞を句の主要部と見なさない方針)
この2つの指針の中でもさらに細かい方針の差というものはあるが, 大きく分けると, 接続詞を主要部とみなすかみなさないかが, まず一つの大きな分岐点となる.
主要部とみなせば, 接続詞自体に新たな特性を仮定することになり, 主要部と見なさないならば, 接続詞が結ぶ他の要素から特性を受け継ぐ分析になっていく.
等位構造の勉強をする際には, こういった観点にも気をつけながら勉強を進めることが重要である.
参考文献
- Progovac, L. (1998). Structure for coordination: Part I. Glot International, 3,