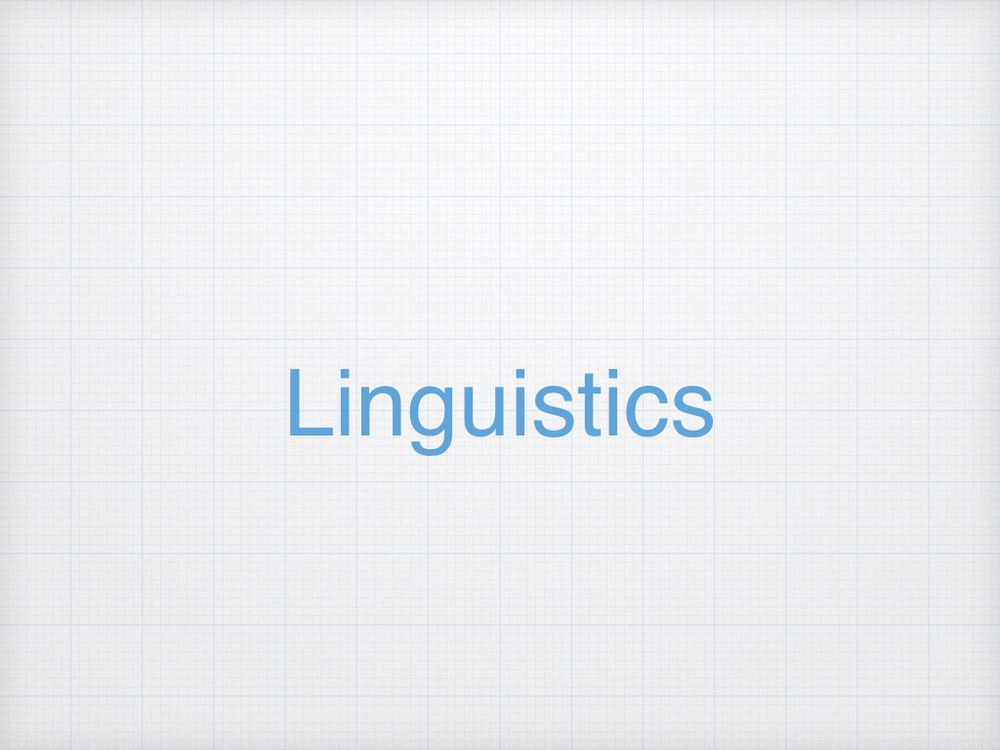併合の仕組み
現在の生成文法の最新理論であるミニマリストプログラムにおいては, Merge (併合) を基本に理論が構築されている. このMergeは非常にシンプルがゆえに, 複雑な構造を持っていないように一見するとそう見えるが, その内実は改めて整理する必要がある. Ishi & Goto (2024) は, この内容を非常にわかりやすくまとめているため, 以下に引用する.
併合は, 一般的なProto演算である「集合形成」(Form Set) に「第三要因」と呼ばれる「自然法則」(特に計算処理システムの最適性および効率性などに関わる科学全般に認められる一般原理) と「第一要因」と呼ばれる「言語固有の条件」(Language Specific Conditions, LSCs) が加わることによって導出される集合形成演算 (set-formation operation) の一種だと考えられている.
(Ishi & Goto, 2024, p. 43)
この引用からわかるように, Merge自体は集合形成能力であり, そこに2つの要因, 自然法則と言語固有の条件が追加されることで実現する演算である. この観点は, 研究を行う上で重要な視点である.
参考文献
- 石井, 透,後藤, & 亘,小町. (2024). 極小主義における説明理論の挑戦: 最適最小性が導く併合とコピー演算.