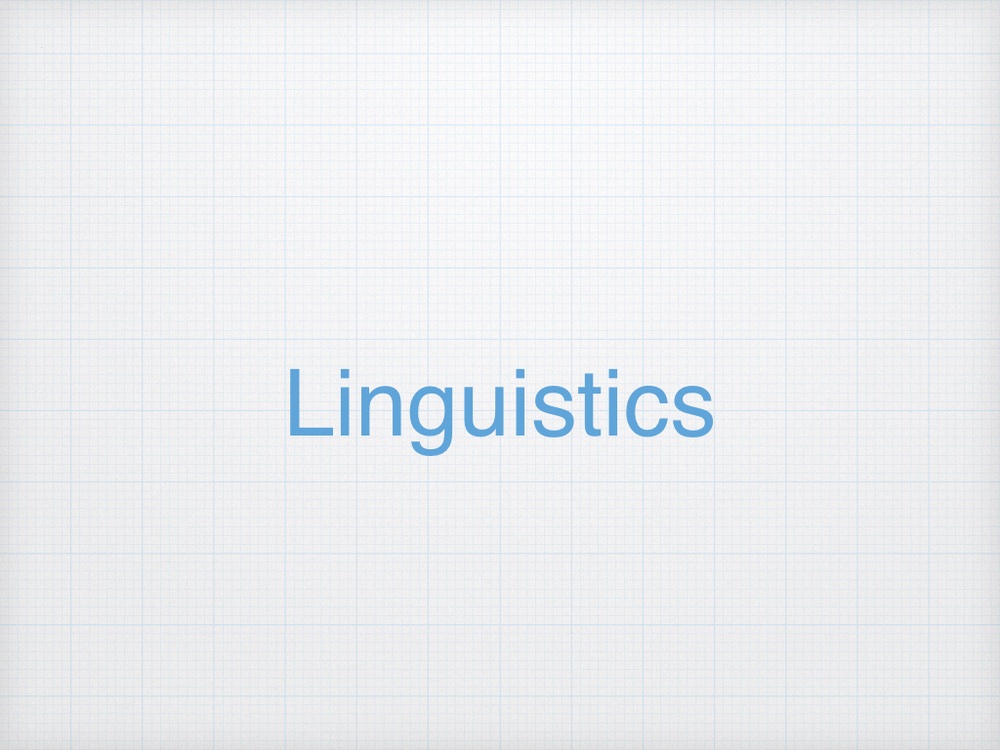出力と入力の相関関係
言語とは, 人間にとってあまりにも身近な存在であるため, その本質的な特性が当然のものとして錯覚されることがある. しかし, こうした言語の特性を冷静に観察し, 記述することは, 言語学にとって極めて重要である. また, 言語学を専門としていない者にとっても, 言語の再発見は興味深い洞察を提供し得るだろう.
Imai et al. (2019) は, 人間の言語における入力体系と出力体系の関係性について重要な指摘を行っている.
ただし、チョムスキーの立場とフォウダーのそれとのあいだには、上記の2つの付随的な主張に関して、違いがあることを認識しておくことが重要である。第1に、言語は視覚や味覚とは違い、単に入力体系であるだけではなく、思考の表現と伝達に連動されている出力体系という核心的機能を持っているという点だ。さらにこの出力体系は入力体系と相関関係にあることがあきらかだ。なぜなら、しゃべれるのは1つの言語だけで、理解できるのはもう1つ別の言語だけ、という人間はいないからだ。この2つの体系に共通するものは、必然的に、認知的・中央システムに属する。したがって言語の大きな部分が「中央的」なわけである。
(Imai et al., 2019)
この指摘は, 言語研究において極めて重要な意義を持つ. 言語の入力体系と出力体系が密接に結びついているという事実は, 言語習得過程における両者の相互依存関係を示唆しているからである. また, 言語の特性をこうした形で言語化する試み自体も, 言語学における本質的な課題の一つであるといえる.
参考文献
- 今井, 中島, 西山 & 外池. (2019). チョムスキーの言語理論: その出発点から最新理論まで.