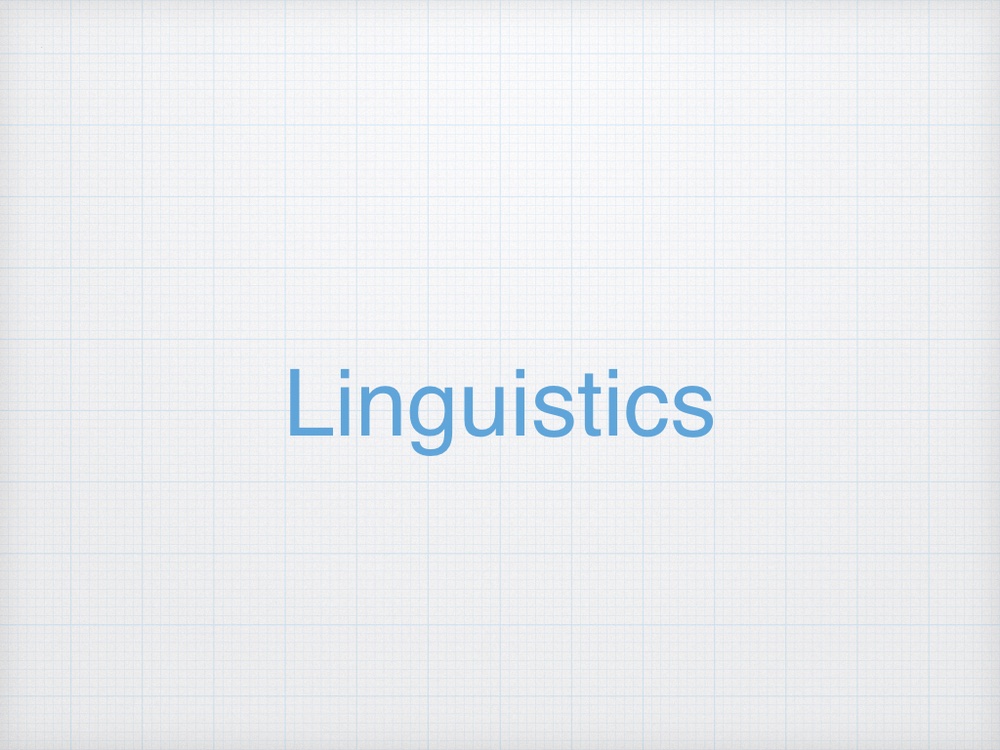言語の運用を見る必要性について
以前の投稿で, 人間の言語能力はLinguistic performance (言語運用)とLinguistic competence (言語能力) に区別することができるということを見た.
生成文法では, 主に言語能力について重視して研究を進めるが, Nakatani (2021)は言語運用の重要性について極めて重要な指摘をしている.
(前略)…なぜ言語運用メカニズムまで関心を広げる必要があるのかを考えてみよう。まず根本的な方法論的問題として、言語能力・知識の研究はこれまで主に内省による文法性判断を通して行われてきたわけだが、その「内省による文法性判断」自体が言語運用であることに今一度注意されたい。言語能力なり知識なりを解剖学的に直接観察することはできないわけだから、言語刺激に対する直観的な文法性判断という言語運用の窓を通してしか、言語能力・知識の研究はできないのは当然のことである。つまり、言語知識と言語運用を区別する必要があるといっても、言語知識は言語運用というフィルター越しにしか見ることができないのである。
(Nakatani, 2021, p. 126)
我々の言語は, 運用を通してしか確認することができない. これは現代の技術を踏まえると正しい指摘であり, だからこそ我々は言語運用と言語能力を区別はしていても, 主に研究したい言語能力に関しては, 一度言語運用というフィルターを通す必要が発生する. つまり, 現状ではどうしても除外することのできない通過点が存在しているようなものである. この点に留意しておかないと, 言語能力の本質的な部分を見誤る可能性がある.
参考文献
- 中村, 岸本, 秀樹, 毛利, 史生, & 中谷健太郎.(2021) 統語論と言語学諸分野とのインターフェイス