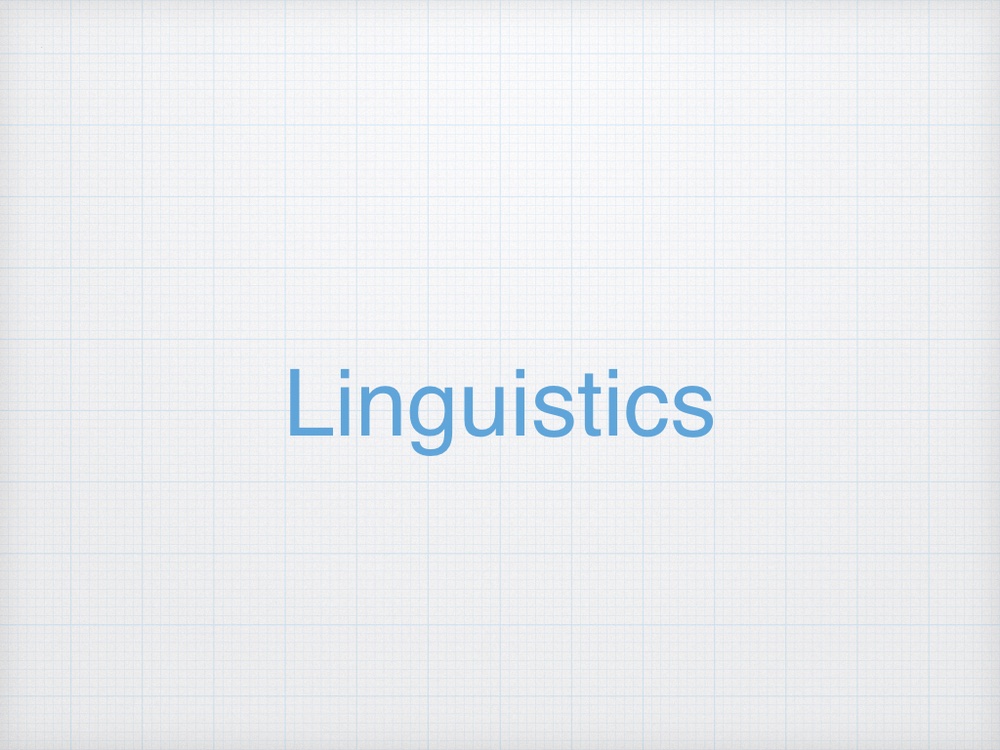言語運用と言語能力
人間は言語をコミュニケーションで扱う際, うまく口が回らずに噛んでしまったり言い間違いをしたりするケースが多々ある. しかし, 我々がそれを間違いだと判断できるのはなぜであろうか. 口が回らずに噛んでしまう場合は, それが明らかに間違いであることがわかる.
他方で次のような文を見たとき, 日本語の母語話者なら1の文は文法的に正しく2の文は文法的に誤っていることが一瞬でわかるが, 日本語の非母語話者なら, これは両方が正しく見えることもあるかもしれない.
- 太郎がご飯を食べた.
- *太郎をご飯を食べた.
一方で, 2の文が文法的に誤っていることが分かったとしても, 1と2の文は文字で見れば一文字違いであり, 会話中で言い間違えて発話をする可能性も十分あり得る単位である. 他方で, 母語話者たちはこれが誤りだとわかっていながらも, 会話中であればわざわざ指摘をすることもなく, 互いに暗黙のうちに理解をして話を進めることができるであろう.
つまり, 意味は理解できていても, 文法的な誤りを判断できているわけである.
これはLinguistic performance (言語運用)とLinguistic competence (言語能力) に切り分けると説明がつく.
口が回らず噛んでしまったり言い間違いをしたりすることは言語の運用上の問題であり, 本質的な言語能力を別途想定すれば, 会話中に起きた誤りは運用ミスであり, 他方で理解をする際には本質的な言語能力に照らし合わせて考えていると想定できる.
参考文献
- 今井, 中島, 西山 & 外池. (2019). チョムスキーの言語理論: その出発点から最新理論まで.