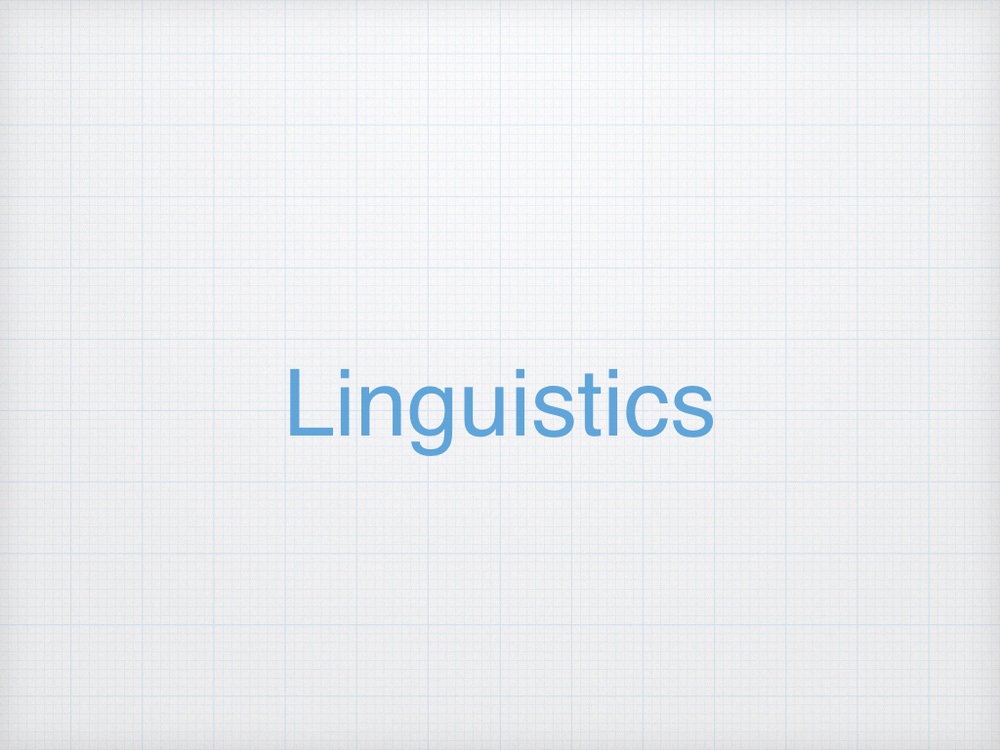構造という言葉の重要性
理論言語学では, 言語の構造というものを考える. しかし, 一般的に構造という場合, 例えば建物の構造や機械の構造など実態を伴ったものを想定する場合が多い. 他方で, 言語の構造というのは, そういった実態を伴わないものである. この部分を非常に巧みに表現した名文があったので(Tsuboi & Hayase, 2020)から引用したい.
ここで考えておかなければならない大きな問題がある。建物のような構造体が特定の構成要素の固定した形での組み合わせという、恒常性のある静的な実体として存在するのに対して、言語のあり方はそれとは大きく異なる。音韻的なものであれ意味的なものであれ、言語の「構造」は時間軸に沿って展開するニューロン群の一定パターンでの発火によって実現されるだけのものであり、同じ「構造」という言葉が用いられても、具象物の構造体の場合とはそれが指すものは大きく異なる。
(Tsuboi & Hayase, 2020, pp. 11-12)
この文は言語の構造を考える上で, 常に念頭に置かなければならない非常に重要な点を指摘している. この著作は, 認知言語学に関しての内容が主となっているので, 生成文法とは異なっている点はあるものの, 共に理論言語学を構築していくためには, こういった構造に対する現実的なイメージを持つことが重要になるであろう.
参考文献
- 加賀, 信広, 西岡, 宣明, 野村, 益寛, 岡崎, 正男, 岡田, 禎之, & 田中, 智之 (編著), 坪井, 栄治郎, & 早瀬, 尚子 (著), & 坪井, 栄治郎 (監修). (2020). 最新英語学・言語学シリーズ13 認知言語学(1): 認知文法と構文文法. 開拓社.